法事でダメな日はある?避けるべき理由と日取りの決め方を解説
- 宗教法人迎福寺
- 2025年4月22日
- 読了時間: 13分

▶︎1. 法事で「ダメな日」ってあるの?基本からわかりやすく解説

1.1 法事とはどんな意味?いつ行うもの?
法事とは、亡くなった方を供養するための大切な仏教行事なんです。
家族が集まり、故人の冥福を祈る場として、昔から日本で大切にされてきました。 四十九日、一周忌、三回忌といった節目ごとに行われるのが一般的で、命日やそれに近い日程で日取りを決めることが多いですね。
法事では、お寺に依頼してお経をあげてもらい、その後に会食をするという流れがよくあります。 最近では、家族だけの少人数で行う「家族法事」も増えていて、形式よりも気持ちを重視する方が増えているんですよ。
地域や宗派によって多少異なりますが、基本的には以下のような時期に行われます。
法事の種類 | 行う時期の目安 |
四十九日(七七日忌) | 亡くなってから49日目 |
一周忌 | 亡くなってから1年後 |
三回忌 | 亡くなってから2年目 |
七回忌・十三回忌など | その年の命日前後 |
これらの日程は、故人への想いを形にする「節目の機会」として大切にされています。
1.2 「ダメな日」って具体的にどんな日なの?
「この日は法事に向かない」と言われる日には、いくつかの理由があるんです。
よく耳にするのは「仏滅」や「友引」のような六曜の考え方ですね。 特に年配の方や親族の中には「縁起を担ぎたい」と思う方も多いので、気にされるケースがあります。
また、以下のような日も避けられることがあるんですよ。
お盆やお彼岸の時期:お寺が混み合う、または他の行事と重なるため
年末年始:喪に服す期間を避けたいと考える方も
親族の都合が悪い日:どうしても集まれない日
ですが、実際には「この日にやってはいけない」という明確な決まりはないんです。
あくまで「気になる方がいるなら配慮する」というのが基本の考え方になります。
1.3 法事の日取りを気にする理由とは?
多くの方が法事の日にちを気にするのは、周囲への思いやりがあるからなんです。
たとえば、「仏滅を選んだら縁起が悪いと思われないかな?」とか、「友引にやると不吉って言われない?」など、 参加する親族の気持ちを大切にしたいという思いから、日取りを慎重に選ぶ方が多いです。
また、お寺の予定や法要の段取りも関係してきます。 希望する日がすでに埋まっていたり、お坊さんが別のご法事に出ていたりすることもありますよね。
だからこそ、「気にしすぎなくてもいいけれど、できるだけ丁寧に決めたい」と思うのが自然なんです。
▶︎2. 法事を避けたほうがいいとされる日とは

2.1 六曜における「仏滅」や「友引」は本当にNG?
「仏滅だからダメ」「友引だから縁起が悪い」…そんな声、聞いたことありませんか?
六曜は「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の6つからなる暦の分類です。 もともとは中国の暦注から伝わったもので、実は仏教とは直接の関係がありません。
ですが、日本では冠婚葬祭など人生の節目で六曜を参考にすることが多く、 法事においても「仏滅」や「友引」は避けるべきだと考える方が今でも一定数いらっしゃいます。
仏滅:字の印象から「仏が滅する=不吉」と連想されがちですが、本来は「すべてがリセットされる日」という意味。再スタートに向いているとも言われています。
友引:葬儀を避ける日として有名ですが、「友を引く」という言葉が独り歩きし、法事も避けられる傾向にあります。
ですが、実際のところ、宗教的な意味合いはほぼないとされていて、 お寺の側でも「気にされるなら避ければよい」という柔軟なスタンスが主流なんです。
六曜を重視するかどうかは、親族の価値観によって大きく変わります。 たとえば、高齢のご親族が「友引の日にはやめておきたい」と言えば、その気持ちを尊重するのも一つの思いやりです。
形式にとらわれるよりも、「皆が安心して集まれる日かどうか」が大事だと思いませんか?
2.2 お盆やお彼岸など、時期的に避けられることが多い日
「その時期はちょっと…」と言われがちな理由は、意外と現実的なものだったりします。
お盆やお彼岸は、ご先祖様を供養するための大切な時期。 この時期にあわせて、故人のお墓参りをしたり、お寺にお参りする方が多いですよね。
ですが、この「仏事が集中する時期」だからこそ、法事の日程としては避ける傾向もあるんです。
その主な理由はこちらです。
お寺の予約が取りづらい:お盆・お彼岸はお坊さんが各家をまわるため、法事の時間が取りづらくなります。
家族の予定が詰まりやすい:学校の夏休み、帰省、旅行などと重なり、参加が難しくなることも。
精神的な負担の軽減:仏事が重なると、「またか…」と疲れを感じる人もいます。
逆に、「みんなが集まりやすい時期だからこそ法事にちょうどいい」という声もあり、これはご家庭ごとの考え方次第です。
大切なのは、「形式的に避ける」のではなく、目的や状況に応じて柔軟に判断すること。 無理なく心を込めた供養ができるタイミングを見つけるのが一番なんです。
2.3 宗教・宗派や地域によって違う「ダメな日」
「うちはそれでいいけど、あちらはダメらしいよ?」そんな違いが生まれるのが、この宗派や地域の慣習です。
たとえば、同じ仏教でも宗派によって考え方が大きく異なります。
天台宗や浄土宗などは、比較的六曜を気にせず柔軟に対応する傾向があります。
一方で、地域によっては「月の初めは法事を避ける」「13日は良くない日」といった土地独特の言い伝えが残っているところも。
こうした風習は、仏教そのものよりも民間信仰や土地の文化が色濃く影響していることが多いんです。
また、地方によっては「法事の後には必ず食事を振る舞うべき」「命日より前倒しが常識」など、 細かな作法が大切にされているところもあります。
それぞれの習わしに「正解・不正解」はなく、一番大事なのは「納得して安心できるやり方を選ぶこと」なんです。
困ったときは、直接お寺に相談してみてくださいね。 迎福寺のように、丁寧に教えてくれるお寺なら、初めてでも安心して決められます。
2.4 家族や親族の都合も「避けたほうがいい日」になる理由
形式より、家族の事情。これ、実は一番多い「ダメな日」の理由かもしれません。
法事というと、「仏滅を避けるべき」「お彼岸を外すべき」といった話が先に来がちですが、 実際に一番多いのは「みんなの都合がつかないから」という理由で日程を変更するケースなんです。
たとえば、
子どもが受験やテスト期間
親族の一部が長期出張中
高齢の親族が寒さに弱く冬の移動が難しい
海外から来る親戚がビザの関係で来日できる時期が限られている
など、人それぞれの事情が「その日は無理」という判断につながることが多いんです。
そして、こうした都合を無視して形式だけを優先してしまうと、誰かが無理をしたり、後々わだかまりになったりすることも。
法事は「故人の供養」でもありますが、それ以上に「家族や親族の心を通わせる場」でもありますよね。 だからこそ、みんなが無理なく集まれる日、心から参加できる日が、「最も良い日」になるのではないでしょうか。
▶︎3. 法事の日取りを決めるときに気をつけたいこと

3.1 お寺の予定や僧侶の都合をどう確認する?
法事は「僧侶の時間ありき」で決まる行事。まずはお寺への相談が出発点です。
多くの方が見落としがちなのが、お寺側のスケジュール確認です。 「この日で決めた!」と親族の予定を固めたあとに、お寺へ連絡して「その日はいっぱいです」と言われるケース、実はとても多いんです。
とくに避けたほうがいいのが、以下の時期の直前予約です。
お彼岸・お盆の前後
年末年始
土日祝日(希望が集中する)
この時期は、お寺では他の法要や参拝の予定がびっしり詰まっていることも。 「予約が取れない」だけでなく、「僧侶が複数法事を掛け持ちしていて、時間が短縮される」こともあるんです。
おすすめの流れは、まず第一希望・第二希望を決めてから、お寺に電話やメールで相談すること。
最近ではホームページから予約フォームが設けられているお寺もありますし、 菩提寺がある場合は、檀家用の連絡先や受付時間が決まっていることもあります。
また、以下のような確認事項も忘れずに伝えるとスムーズですよ。
法事の種類(例:三回忌、一周忌など)
参加予定人数
会場(自宅 or お寺)
お食事の有無(会食の場所が必要か)
「早めの連絡が、希望通りの日程につながる」これが何より大事なポイントです。
3.2 親族とのスケジュール調整をスムーズにするコツ
誰かが音頭を取らないと、法事の予定はなかなか決まりません。だからこそ、段取り上手が大切です。
親族が多い場合、調整に時間がかかるのは当たり前。 「みんなの予定を聞いてから日を決めよう」と思うと、なかなか決まらずどんどん時間が過ぎてしまいます。
そんなときは、次のような工夫をしてみましょう。
◆ 決める立場の人が主導して進める
喪主や代表者が「この日を考えています」と方向性を出すと、全体が動きやすくなります。 候補日をいくつか出してアンケート形式でLINEやメールで共有すると、返信も集まりやすいですよ。
◆ 「絶対全員集合」を目指さなくてもいい
誰かが参加できないと「申し訳ない」と感じるかもしれませんが、 遠方の親族や高齢の方など、それぞれ事情があります。
来られない方には「後日、お線香だけでも上げてくれれば」と伝えることで、無理のない法事が実現します。
◆ 小さなお子さんや高齢の方にも配慮
例えば、午前中に行うと移動がラク、会食を控えることで子連れでも参加しやすいなど、 参加者の立場を想像しながら時間帯や内容を調整すると、自然と集まりやすい雰囲気が生まれます。
「全員の気持ちが整う形を探すこと」が、円満な法事の第一歩です。
3.3 急に日程変更が必要になった場合の対応方法
突然の変更は焦りますが、正直に、丁寧に対応すれば大丈夫です。
予定していた日に大きな予定が入ってしまったり、体調不良や天候不順、災害などで変更を余儀なくされることもありますよね。 法事だからといって、絶対にその日にしなければならない決まりはありません。
急な変更時にやるべきことは、次の3つ。
手順 | 内容 |
① お寺にすぐ連絡 | 空いている別日を確認し、調整依頼を |
② 親族に事情説明 | 連絡手段を統一(グループLINEなど)して迅速に伝える |
③ 会食会場がある場合 | キャンセルや日時変更の連絡を早めに |
僧侶の方も人間ですから、やむを得ない事情にはしっかり対応してくださいます。
逆に、直前で連絡なしのキャンセルはお寺にとっても迷惑になってしまうので、そこだけは気をつけたいですね。
また、「急な変更で全員が再集合できない」というケースもあると思います。 その場合、代表者だけで簡易的にお経をあげてもらう「縮小法事」も選択肢になりますし、 オンラインでのリモート参列を取り入れているお寺も増えていますよ。
一番大切なのは、無理せず、心を込めて供養すること。日程の変更があっても、それが故人に対する失礼にはなりません。
▶︎4. 「法事で本当に大切なのは気持ち」 心を込めた供養のすすめ
4.1 日にちよりも「心」が大事にされる理由
法事で一番大切なのは「いつやるか」より「どう向き合うか」なんです。
たしかに「仏滅は避けようかな」「お彼岸は混むしなぁ」と日取りに悩む方も多いですよね。 でも、どんな日であっても、故人を想う気持ちが込められていれば、それが一番の供養になります。
ご家族の都合や心の準備が整ってからでも遅くありません。 「みんなで集まって手を合わせられた」「改めて思い出を語れた」そんな時間こそが、心を癒してくれるものです。
仏教の教えにもあるように、形だけでなく「真心」をもって向き合うことが尊ばれるんですよ。
4.2 迎福寺が大切にしている、寄り添う法事の考え方
迎福寺では、どんな方でも安心して供養に臨めるよう、心を込めた対応を大切にしています。
迎福寺は、千葉県印西市にある500年以上の歴史を持つ曹洞宗のお寺です。 「人の癒しの場」として地域と共に歩み、現代の暮らしにも寄り添った仏事を大切にしているんですよ。
法事については、通夜・葬儀・一日葬など、ご希望やご事情に合わせて丁寧に対応されています。 しかも、以下のような特徴があるので安心してご相談できるんです。
仏事に関する費用は事前にお見積もり、不明点も気軽に質問OK
法要には椅子席や空調が整った本堂をご利用可能で、ご高齢の方にもやさしい環境
祭壇や駐車場は無料提供、法要後の食事や供花なども低価格で準備可能
そしてなにより、「形式よりも心」「強制ではなくご縁を大切に」という考え方が、 初めての方や仏事に不安を抱える方にとって大きな安心につながっています。
4.3 初めてでも安心できる、迎福寺での法事サポート
「お寺にお願いするのは初めて」という方でも、迎福寺なら安心なんです。
仏事に慣れていない方にとって、お寺に問い合わせるのはちょっとハードルが高く感じますよね。 でも、迎福寺ではこんな方針があるんです。
宗派を問わず、曹洞宗の法式で丁寧に法事を実施
ご寄進や追加の費用を強要しない明確な運営方針
生活保護や経済的に不安のある方にもやさしく対応
また、少人数での法要には住職が運転する車で送迎もしてくださるなど、 地域に根ざした温かいサポートは本当にありがたいですよね。
「仏事が初めてで不安…」「誰に相談すればいいかわからない…」 そんなときこそ、迎福寺のような親身に寄り添ってくれるお寺が頼りになります。
形式にとらわれず、心を込めた供養を大切にしたいと考えている方には、ぴったりの場所です。
▶︎5. まとめ:法事の「ダメな日」に縛られすぎないで
5.1 最後に伝えたいこと:故人を思う気持ちを大切に
本当に大切なのは「日にち」よりも「心」なんです。
法事の日取りに悩む方はとても多いです。 「仏滅は避けた方がいいの?」「この時期はダメかな?」と、不安になる気持ちもよくわかります。
でも、仏教の教えでは「形よりも心」が重んじられます。 六曜や時期も大切かもしれませんが、それ以上に大切なのは「どう供養するか」「どんな気持ちで手を合わせるか」なんです。
家族が無理なく集まれて、穏やかな気持ちで故人を偲べる日が、あなたにとっての“良い日”になると思いますよ。
「正しい日」より、「あなたらしい供養」を心がけてくださいね。
5.2 不安や疑問がある方は、迎福寺に相談してみてください
迷ったときは、一人で悩まずにお寺に相談してみてください。
初めての法事や、慣れない仏事は、不安や戸惑いがつきものですよね。 そんなときに心強いのが、迎福寺のように親身になってくれるお寺です。
迎福寺では、どんなご相談にも丁寧に対応してくださいますし、 法事の形式や費用についても事前にしっかり説明してくれるので安心です。
特にこんな方にはおすすめです。
「法事の進め方がわからない」
「お布施や準備について相談したい」
「形式にとらわれず、心のこもった供養がしたい」
迎福寺は、地域に根ざしながらも、時代に合ったやさしい法事を提案してくれるお寺です。 困ったことがあれば、まずは気軽に問い合わせてみてくださいね。
故人を偲ぶ大切なひとときを、あなたらしく心を込めて迎えられますように。
▶︎法事の日取りに迷ったら、迎福寺にご相談ください
「法事のダメな日っていつ?」「親族の予定が合わない…」「お寺にお願いするのは初めてで不安…」
そんなお悩みを抱えている方にこそ、千葉県印西市の曹洞宗 天長山 迎福寺をおすすめします。
迎福寺では、形式よりも“心を込めた供養”を大切にし、 それぞれのご家族に寄り添った法事を丁寧にサポートしてくださいます。
初めての方でも安心できる環境と、明るく丁寧な対応が評判です。
日取りのこと、仏事の進め方、費用のことまで、どんなことでも気軽にご相談くださいね。
「自分らしい法事」を一緒に考えてくれるお寺が、ここにあります。

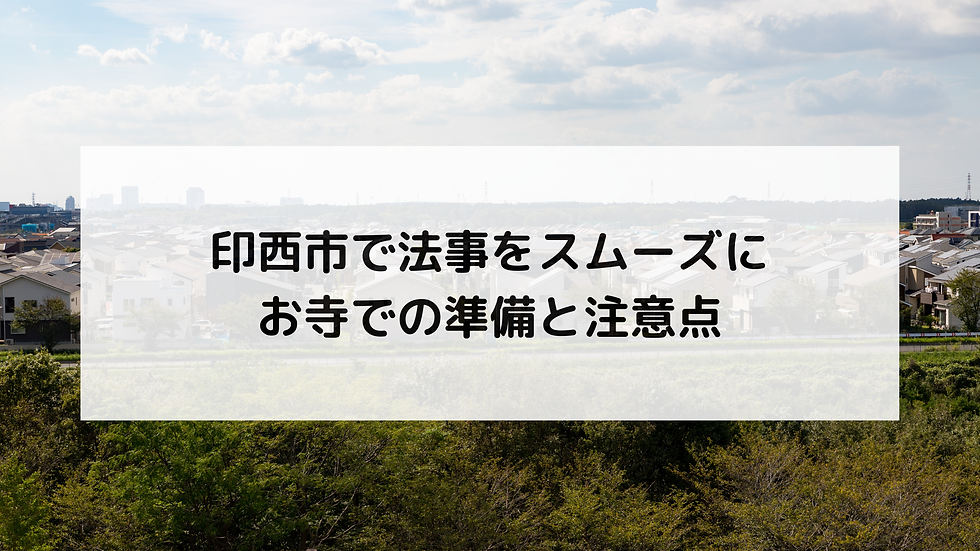

コメント