葬儀が終わったらすることを徹底解説|手続き・供養・相続まで完全ガイド
- 宗教法人迎福寺
- 10月23日
- 読了時間: 16分

▶︎1. 葬儀が終わったらまず知っておきたい基本の流れ

1.1 葬儀後は「終わり」ではない
葬儀が無事に終わると、多くの方が「これで一段落」と感じるものです。 しかし実際には、葬儀は故人を見送る一連の流れのまだ途中にすぎません。 葬儀が終わったあとには、行政手続き・名義変更・供養の準備など、やるべきことが数多くあります。
特に、葬儀後1週間ほどのあいだは、感情の整理がつかないまま様々な手続きに追われる時期でもあります。 たとえば次のような作業が必要になります。
役所での死亡届関連の手続き(年金・保険・世帯主変更など)
銀行口座やクレジットカードの凍結・解約・名義変更
香典返しや弔問へのお礼
本位牌の準備や納骨日の調整
相続の確認や遺品の整理
これらを放置すると、後からトラブルや遅延が発生することもあります。 葬儀が終わったあとこそ、計画的に進めることが大事です。
忙しさや疲れの中で無理をする必要はありませんが、やるべきことを大まかに整理し、家族で分担しながら少しずつ進めることが安心につながります。 「悲しみの時間」と「手続きの時間」を上手に両立させることが、葬儀後を穏やかに過ごす第一歩になります。
1.2 まずやるべき基本の流れを把握する
葬儀が終わった直後は、どこから手をつけていいか迷う方が多いです。 気持ちが落ち着かない中で、たくさんの手続きや準備を一度に進めるのは大変ですよね。
そこで、まずは全体の流れを時期ごとに整理しておくと安心です。 大まかには、次のようなスケジュールになります。
時期 | 主な内容 |
葬儀直後(〜3日以内) | 行政手続きの確認、死亡届提出、世帯主変更、健康保険・年金関連の届出 |
葬儀後1週間〜2週間 | 銀行口座・公共料金・保険などの名義変更、香典返しの準備、弔問者へのお礼 |
四十九日まで | 本位牌の作成、納骨の日程調整、お墓の字彫り、法要準備 |
四十九日以降〜3か月以内 | 相続手続き、不動産・預貯金の整理、確定申告や保険金請求など |
半年〜1年以内 | 一周忌法要、納税関連の最終確認、遺品整理の完了 |
このように、葬儀後の流れは「短期の手続き」と「長期の供養・相続」に分けて考えると進めやすくなります。
よくある失敗としては、
① 行政手続きの期限を過ぎてしまう
② 名義変更を後回しにして口座が凍結される
③ 法要準備を直前に始めて慌てる などがあります。
これらを防ぐためには、次の3つを意識して進めましょう。
優先順位を決めて「早めにやることリスト」を作る
家族で役割を分担する
専門家やお寺など、信頼できる相談先を早めに決める
全体の流れを理解してから動くことで、心にも時間にも余裕が生まれます。 焦らず一つずつ整理していくことが、葬儀後の生活を穏やかに整えるコツです。
▶︎2. 葬儀が終わったあとに必要な行政・手続き関係の準備

2.1 役所での行政手続き一覧(世帯主変更・年金・健康保険など)
葬儀後はまず、役所での手続きを早めに済ませることが大切です。 これらには期限があるため、後回しにすると支給停止やトラブルになることがあります。
主な行政手続きは次の通りです。
世帯主変更:故人が世帯主だった場合、14日以内に届け出を提出
健康保険:保険証を返却し、扶養家族の切り替えや喪失届を提出
年金:受給停止手続き(故人の年金は支給停止、遺族年金の申請も確認)
介護保険:被保険者証を返却し、未払い分や還付の確認
印鑑登録:登録証を返却し、抹消手続き
戸籍・住民票:必要に応じて除籍謄本を取得しておく
注意しておきたいポイントは以下の3つです。
多くの届出は「14日以内」が期限
各手続きで必要な書類(死亡診断書の写し・印鑑・本人確認書類)をまとめて持参する
担当窓口が異なるため、事前に役所へ電話確認しておく
手続きの効率を上げるコツは、
1日でまとめて複数窓口を回れるように準備する
チェックリストを作り、完了項目に印をつけておく
行政手続きは葬儀後の生活を整える第一歩です。 早めの行動で、その後の相続や名義変更もスムーズに進みます。
2.2 銀行口座・公共料金・保険などの名義変更と注意点
葬儀が終わったら、早めに進めたいのが銀行口座や保険、公共料金の名義変更です。 名義変更を放置すると、口座凍結や支払い停止などのトラブルにつながることがあります。
主な手続きの流れは次の通りです。
銀行:死亡届の提出後は口座が凍結されるため、相続人全員の同意書を用意して払い戻しや解約を進める
公共料金:電気・ガス・水道などの契約名義を早めに変更し、支払いが滞らないようにする
保険:生命保険や火災保険などは、受取人や契約者変更の届出を行い、保険金の請求期限(多くは3年以内)を確認する
クレジットカードやサブスク:自動引き落としを止め、不要な契約は解約する
注意しておきたいポイントは以下の通りです。
凍結された口座から公共料金の引き落としができなくなる
保険金請求の期限切れで受け取りを逃すケースがある
手続き先ごとに必要書類が異なるため、事前確認が必要
手続きをスムーズに進めるコツは、
契約書や通帳を一覧化して整理する
家族で分担して複数の窓口を並行処理する
不明点は各機関に電話で確認する
名義変更は「早めの確認」と「整理」が鍵です。 トラブルを防ぎ、安心して生活を整えるためにも、計画的に進めましょう。
2.3 香典返し・挨拶回りのマナーとタイミング
葬儀が終わったあとに行う大切な礼儀が、香典返しと挨拶回りです。 お世話になった方へ感謝を伝える機会でもあり、丁寧に準備しておくことが大切です。
香典返しの基本的なマナーは次の通りです。
贈る時期:四十九日を過ぎた「忌明け」の頃が目安
品物の相場:頂いた香典の半額程度(半返し)
品物の種類:日持ちする食品やカタログギフトなど
のし紙:表書きは「志」、下に喪主の姓を記載
送付方法:遠方の方には配送し、お礼状を添える
挨拶回りを行う際のポイントは以下の通りです。
特にお世話になった方には、香典返しを手渡ししながら直接お礼を伝える
長居はせず、感謝の言葉を簡潔に伝える
挨拶状やお礼状を添えるとより丁寧な印象になる
よくある注意点も確認しておきましょう。
香典帳の整理を後回しにして贈り漏れが出る
時期が遅れ、かえって相手に気を遣わせてしまう
金額の確認ミスで返礼のバランスが崩れる
香典返しは「ありがとう」の気持ちを形にする大切な供養の一つです。 焦らず、相手を思いやる気持ちを大切に準備しましょう。
▶︎3. 葬儀が終わったら行う供養や法要の準備

3.1 本位牌の作成と白木位牌からの切り替え
葬儀で使う白木の位牌は一時的なもので、四十九日までに本位牌を用意するのが一般的です。 本位牌は故人の魂を迎える大切な供養であり、早めの準備が欠かせません。
作成の流れは次の通りです。
お寺で戒名・没年月日・俗名を確認する
仏具店で形や材質(塗位牌・唐木位牌など)を選ぶ
彫刻内容を依頼し、完成後に開眼供養で魂を入れる
よくある注意点は次の3つです。
戒名の文字間違いを防ぐため、依頼前にお寺へ確認
仏壇のサイズを測り、位牌の大きさを合わせる
兄弟姉妹で位牌のデザインを統一しておく
本位牌は故人の新しい居場所を整える大切な供養です。 焦らず丁寧に準備を進めましょう。
3.2 納骨の時期とお墓への字彫り準備
葬儀後は、納骨とお墓の字彫りを準備する時期になります。 多くの場合、納骨は四十九日法要に合わせて行われますが、事情によって百か日や一周忌に延ばすこともあります。
主な準備内容は次の通りです。
菩提寺や霊園に連絡し、僧侶・親族の予定を調整する
火葬場で受け取った「納骨許可証」を用意する
墓地を清掃し、供花や線香などを準備する
骨壺のサイズが納骨室に合うか確認する
墓石に名前や没年月日を彫刻する(字彫りは1〜2週間かかることも)
注意点としては、
字彫りの依頼が遅れると四十九日に間に合わない
彫刻内容の誤字は修正に時間と費用がかかる
雨天などで納骨日を変更する場合は早めに連絡
納骨と字彫りは、故人への最後の贈り物として丁寧に準備することが大切です。
3.3 四十九日・百か日など法要の流れを整理する
葬儀後の供養では、四十九日法要が最も大切な節目になります。 この日は故人が成仏するとされる日で、忌明けの報告と本位牌の開眼供養、納骨を同時に行うことが一般的です。
主な法要の流れは以下の通りです。
お寺と日程を調整し、僧侶の予定を確定する
参列者の人数を確認して、会食や引き出物を手配
本位牌や納骨、字彫りの準備を整える
当日は供花・供物を用意し、読経にあわせて焼香を行う
注意しておきたいポイントは次の3つです。
僧侶の予定確認は2〜3週間前に行う
準備を後回しにすると本位牌や墓石が間に合わない
会食を行う場合は予約を早めに済ませる
四十九日が過ぎたあとは、百か日、一周忌、三回忌と続きます。 法要は故人への感謝を伝え、家族が心を整える大切な時間です。
▶︎4. 葬儀後に行う相続やお金の整理
4.1 相続手続きの基本と期限の考え方
葬儀後には、相続手続きも早めに進める必要があります。 相続は複雑に見えますが、期限を意識して順序立てて進めれば慌てずに対応できます。
主な相続手続きの流れは次の通りです。
相続人の確認(戸籍謄本を取得して法定相続人を特定)
遺言書の有無を確認(公正証書・自筆証書など)
相続財産の把握(預貯金・不動産・保険・証券など)
財産分割協議を行い、全員の同意を得て書面化
不動産・預金・保険の名義変更を実施
期限に関しては、以下の3点を押さえておきましょう。
相続放棄や限定承認は「3か月以内」
相続税の申告・納付は「10か月以内」
準確定申告(故人の所得分)は「4か月以内」
よくある注意点としては、
財産調査が不十分で後からトラブルになる
相続人の一部が連絡を取れず協議が進まない
税務処理を後回しにして期限を過ぎる
相続は早めの情報整理と期限管理が成功のカギです。 迷ったら税理士や行政書士などの専門家に相談するのも安心です。
4.2 不動産・預貯金・保険などの整理方法
相続では、故人が残した不動産・預貯金・保険を整理する作業が中心になります。 これらはそれぞれ手続き先や必要書類が異なるため、項目ごとに分けて進めるのが効率的です。
主な整理の流れは次の通りです。
不動産:登記簿謄本で所有者を確認し、相続登記を法務局で行う
預貯金:各金融機関で残高証明を取得し、相続人全員の同意書を添えて払い戻し
生命保険:保険証券を確認し、受取人が請求書と死亡診断書を提出
その他資産:有価証券や貴金属などは、評価額を一覧化して共有
注意しておきたいポイントは次の3つです。
不動産の名義変更を放置すると売却や管理ができなくなる
銀行口座は凍結されるため、早めに手続きが必要
保険金の請求期限(3年以内)を過ぎると受け取れなくなる
これらをスムーズに進めるコツは、
財産一覧をエクセルなどで整理して可視化する
相続人全員が内容を共有しておく
不明点は金融機関や専門家に確認する
財産を正しく整理することが、家族間のトラブル防止につながります。
4.3 専門家に相談すべきポイントと注意点
相続や手続きの中には、個人だけでは判断が難しい場面も多くあります。 そんなときは、早めに専門家へ相談することで時間と労力を大きく減らせます。
主な相談先と役割は次の通りです。
税理士:相続税の申告・節税対策・財産評価の計算
弁護士:遺産分割トラブルや遺言書の有効性確認
行政書士:相続関係書類の作成や各種届出のサポート
司法書士:不動産の名義変更や登記関連手続き
相談のタイミングで注意したいポイントは以下の3つです。
財産の全体像がつかめない段階で自己判断しない
期限(相続放棄3か月、税申告10か月)を過ぎないように行動
相談内容を家族で共有し、情報の食い違いを防ぐ
専門家を選ぶ際のコツも押さえておきましょう。
初回相談が無料の事務所を利用して比較する
相続に強い分野の実績を確認する
料金体系を事前に明確にしておく
専門家の力を借りることで、複雑な相続も確実に進められます。 「自分たちで全部やらなければ」と抱え込まず、安心できるサポートを活用しましょう。
▶︎5. 葬儀が終わった後の心と暮らしの整え方
5.1 気持ちの整理と喪の期間の過ごし方
葬儀を終えたあと、多くの方が感じるのが深い喪失感と疲れです。 手続きや法要を終えるまで気が張っていた分、ようやく気持ちが追いつく時期でもあります。
喪の期間は、無理をせず心と体を休める時間と考えることが大切です。
気持ちを整えるための過ごし方のポイントは次の通りです。
毎日を無理に元通りに戻そうとせず、生活リズムをゆっくり取り戻す
故人の写真や遺品をそばに置き、感謝の言葉を伝える時間をつくる
家族や友人と会話をすることで、悲しみを一人で抱え込まない
散歩や軽い運動を取り入れ、気分を整える
よくある注意点としては、
無理に「元気に振る舞おう」として疲れてしまう
忙しさを理由に気持ちを整理する時間を取らない
法要が終わったあとに一気に虚しさが押し寄せる
喪の期間をどう過ごすかに正解はありません。 焦らず、故人を思いながら日々を丁寧に過ごすことが供養にもつながります。
5.2 忙しい中でも無理なく進めるスケジュール管理術
葬儀後は、手続きや法要などでやることが一気に増える時期です。 仕事や家事と並行して進めるのは大変ですが、スケジュールを整理すれば焦らず対応できます。
無理なく進めるためのコツは次の通りです。
「今週・今月・半年以内」と期間を3段階で区切って予定を立てる
行政手続きや法要など、期限のあるものを優先してスケジュールに組み込む
手帳やスマホアプリでタスクを可視化し、家族と共有する
書類・連絡先・領収書などを一つのファイルにまとめて保管する
よくある失敗と対策も知っておくと安心です。
期限を把握しておらず、手続きが遅れて再提出になる
→ 優先度リストを作って確認を習慣化する
家族で情報共有ができず、手続きが重複する
→ 共有メモやグループLINEなどで報告を統一する
無理に一人で抱え込み、体調を崩す
→ できる範囲で家族や専門家に協力を依頼する
スケジュールを「見える化」するだけで、手続きの負担がぐっと減ります。 焦らず、一歩ずつ整理していきましょう。
5.3 家族で分担して乗り越えるコツ
葬儀後の手続きや供養は、ひとりで抱えるには負担が大きいものです。 家族で協力して分担することで、心の負担も軽くなり、手続きもスムーズに進みます。
効果的に分担するためのポイントは次の通りです。
手続きや法要などの「やることリスト」を作り、担当を明確にする
行政関係、金融関係、法要準備など、分野ごとに担当者を決める
家族LINEや共有ノートを活用し、進捗を見える化する
忙しい人には「確認だけ」「書類提出だけ」など小さな役割を任せる
よくある失敗とその対策も押さえておきましょう。
誰が何を担当しているか分からず、手続きが重複する
→ 共有表を作り、完了済み項目をチェック
家族の意見が合わず話が進まない
→ 一度に決めようとせず、段階的に相談を進める
感情的になり話し合いが停滞する
→ お寺や第三者を交えて冷静に整理する
「誰か一人が頑張る」より「みんなで支え合う」方がずっと早く整います。 協力しながら、少しずつ前に進んでいきましょう。
▶︎6. 葬儀が終わったあとも安心できる迎福寺の供養サポート
6.1 曹洞宗の教えに基づく供養の考え方
葬儀が終わったあとも、供養は日々の暮らしの中で続いていくものです。 曹洞宗では、「日常の中にこそ仏の教えがある」と考え、静かに手を合わせる時間そのものが供養とされています。
曹洞宗の供養の基本は次の通りです。
毎日の朝夕に仏壇へお線香をあげ、感謝の心で手を合わせる
年忌法要を通して、家族が集い故人を偲ぶ時間を持つ
お墓や仏壇をきれいに保ち、日常の中で故人を思う
他者への思いやりや感謝の実践を、供養の一つと考える
曹洞宗の供養の特徴として、
形式よりも「心」を重視する
故人を偲びながら、自分自身の生き方を見つめ直す
法要は“感謝を伝える機会”であり、義務ではない という点が挙げられます。
よくある誤解として、「供養は特別な行事」と思われがちですが、 日々の祈りや感謝の行動そのものが立派な供養です。 無理をせず、自分のペースで心を込めた供養を続けることが大切です。
6.2 迎福寺で行える法要・納骨・墓地管理の特徴
迎福寺では、曹洞宗の教えに基づいた丁寧な供養と法要を行っています。 葬儀後も安心して供養を続けられるよう、法要・納骨・墓地管理まで一貫したサポート体制が整っています。
主な特徴は次の通りです。
四十九日・一周忌・三回忌など、各法要を宗派の形式で丁寧に執り行う
本堂や法要室で、少人数から家族単位まで柔軟に対応可能
納骨堂・墓地の管理を自寺で行い、供花や清掃も相談できる
遠方の方には、読経のみや合同法要などの案内も可能
迎福寺の法要・供養サポートの強みは、
僧侶が直接対応し、形式だけでなく「心を込めた供養」を重視
境内が常に整備され、穏やかな環境でお参りできる
法要から納骨、墓地管理まで一か所で完結できる安心感
迎福寺では、故人と向き合いながら、家族が心を落ち着けて供養できる環境が整っています。 葬儀後の法要や納骨の相談も、早めにお寺へ連絡しておくと安心です。
6.3 葬儀後の相談ができる迎福寺のサポート体制
迎福寺では、葬儀が終わったあとも安心して過ごせるよう、供養・法要・墓地管理に関する相談体制を整えています。 遺族が抱える「何から始めたらいいか分からない」という不安を、丁寧な説明とサポートで解消してくれます。
主な相談内容は次の通りです。
四十九日や一周忌など、法要の日程・内容の相談
本位牌や納骨、墓石の字彫りなど供養準備の案内
墓地の使用・管理・永代供養に関する問い合わせ
遠方在住の家族向けのオンライン相談や郵送対応
迎福寺のサポート体制の特徴は、
僧侶が直接対応し、宗派や供養の疑問に一つずつ回答
事務手続きも一緒に確認でき、初めての方でも迷わない
供養の考え方から実務的な準備まで総合的にサポート
また、年中無休(8:30〜19:00)で対応しており、忙しい方でも都合に合わせて相談できます。 迎福寺は、葬儀後の不安を安心に変える“寄り添うお寺”です。 供養や法要の準備に迷ったときは、気軽に相談してみましょう。
▶︎7.まとめ
ここまで、葬儀後に必要な手続きや供養の流れを整理してきました。 改めて振り返ると、葬儀が終わってからもやることはたくさんあります。 しかし、順序を理解して進めれば、焦らず落ち着いて対応できます。
整理しておきたいポイントは次の通りです。
行政手続きは14日以内を目安に行う(世帯主変更・年金・保険など)
銀行や公共料金の名義変更、香典返しの準備を並行して進める
本位牌の作成や納骨、法要の日程を早めに調整する
相続や財産整理は期限を意識し、専門家への相談も検討する
家族で分担しながら無理なく進めるスケジュールを立てる
供養は形式よりも「心を込める」ことを大切にする
葬儀が終わったあとに残るのは、故人を思う静かな時間です。 手続きを整え、供養の形を整えることは、残された家族の心を整えることでもあります。
慌ただしい時期がひと段落したら、ゆっくりと故人を思い出し、穏やかに手を合わせる時間を持ちましょう。
その一歩が、新しい日常を歩み出すための大切な区切りになります。
▶︎葬儀後の供養・お墓の管理も安心の迎福寺
迎福寺では、法要や納骨はもちろん、墓地の管理や清掃まで一貫してサポートしています。
初めての方でも安心して相談できるよう、僧侶が丁寧にご案内します。
詳細は迎福寺公式サイトをご確認ください。

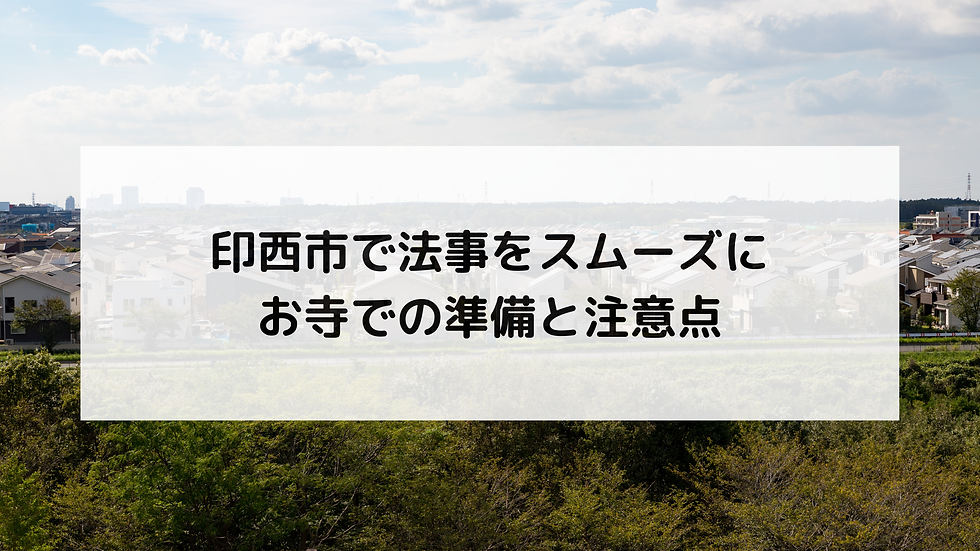

コメント