永代供養の費用相場はどのくらい?管理料不要で安心の選び方ガイド
- 宗教法人迎福寺
- 2025年11月14日
- 読了時間: 15分

▶︎1. 永代供養とは?意味と特徴をやさしく解説

1.1 永代供養の基本的な仕組み
永代供養とは、お墓を継ぐ人がいない方のために、寺院などが永続的に供養と管理を行う方法です。近年では後継者不足やライフスタイルの変化により、この供養方法を選ぶ方が増えています。
一般的なお墓では、家族や子孫が代々お墓を守り、掃除や管理料の支払い、法要の手配などを行います。これに対して永代供養は、お寺や霊園が供養・管理を代行してくれるため、継承者がいなくても安心してお任せできます。
また、契約時に費用を一括で納めるケースが多く、後からの管理費が不要な永代供養を選ぶことで、将来的な金銭トラブルを防ぐことができます。
管理料が発生する場合は、支払いを行っていた方が亡くなった後に継続が難しくなるケースもあるため、最初から「管理料がかからないタイプ」を選ぶのが安心です。
永代供養では、遺骨を一定期間安置した後に合祀(他の方と一緒に埋葬)する形を取ることもあります。その際、合祀墓が整備されている寺院を選ぶと、将来的な供養も円滑に行える点が魅力です。
1.2 一般的なお墓との違い
一般的なお墓は「家族単位」でお墓を建て、代々受け継ぐ形が一般的です。毎年の管理料や法要の準備など、家族の負担が続く点が特徴です。
一方、永代供養では以下のような違いがあります。
契約時に費用を納めれば、その後の管理料が不要なケースが多い
供養や清掃をお寺が行ってくれるため、遠方に住んでいても安心
継承者がいなくても、永続的に供養が続く
つまり、永代供養は「家族がいなくても供養を受けられる方法」として注目されています。お墓を維持する手間がなく、安心してお寺にお任せできる点が最大の特徴です。
1.3 永代供養が選ばれる背景
近年、永代供養を選ぶ方が増えている背景には、社会の変化があります。核家族化や少子高齢化が進み、お墓を受け継ぐ人がいないという家庭が増えています。さらに、都市部での住宅事情や、実家から離れて暮らす人が多いことも理由のひとつです。
永代供養を選ぶことで、次のような安心感が得られます。
後継者がいなくても、お寺が供養を続けてくれる
管理料の支払いが不要で、将来の金銭トラブルを防げる
お盆・お彼岸・回忌法要などもお寺が行ってくれる
特に、供養に行けなくてもお寺が季節ごとの法要を執り行ってくれる仕組みがあると、より安心です。忙しい現代の暮らしの中でも、大切な人を静かに見守ってもらえる――そんな心の支えが、永代供養が選ばれている理由です。
永代供養は、「お墓を守れない不安」を「お寺に託す安心」に変える新しい供養の形です。
▶︎2. 永代供養の費用相場と内訳

2.1 永代供養の費用相場の目安
永代供養の費用は、全国的に見ると10万円〜50万円前後が一般的な相場といわれています。金額には幅がありますが、それは供養の形式や納骨の方法によって内容が異なるためです。
たとえば、複数の方と一緒にお骨を納める「合祀タイプ」は比較的費用を抑えられます。
一方で、一定期間個別で安置する「個別タイプ」や、専用の墓石・納骨堂を設ける場合は費用が上がります。
一般的な目安としては以下のようになります。
永代供養の形式 | 費用相場(目安) | 特徴 |
合祀(ごうし)型 | 約5万〜20万円 | 他の方と同じ墓に納骨されるため費用を抑えられる |
個別型 | 約20万〜50万円 | 一定期間、個別の区画で安置される |
納骨堂型 | 約30万〜70万円 | 屋内施設で管理され、天候に左右されにくい |
樹木葬型 | 約20万〜50万円 | 自然の中で埋葬される形式で人気が高い |
このように、形式によって費用は異なりますが、契約時にすべての費用を一括で支払うケースが多いのが永代供養の特徴です。
そのため、後から管理費などが発生しない仕組みを選ぶことが、将来的な安心につながります。
2.2 費用に含まれる内容と注意点
永代供養の費用には、主に以下のような内容が含まれています。
納骨料(お骨を納めるための費用)
永代供養料(寺院による継続的な供養のための費用)
合祀や個別区画の使用料
供養塔や納骨堂の維持費
法要や読経の費用
このように多くの項目がまとめて含まれていますが、寺院や霊園によって内容は異なります。注意したいのは、管理料が別途かかる永代供養を契約してしまうケースです。
永代供養は「継承者がいない方のための供養方法」です。したがって、管理料を毎年支払う仕組みでは、支払いをしていた方が亡くなった後に金銭的な問題が生じることもあります。
こうしたトラブルを避けるためには、最初に管理料が発生しない永代供養を選ぶことが大切です。
また、費用の中に「永代供養のみ含まれていて納骨料が別途」のようなパターンもあります。契約前に見積書を確認し、含まれる項目を細かくチェックしておきましょう。
2.3 永代供養の種類別(合祀・個別・樹木葬・納骨堂など)相場比較
永代供養にはいくつかの形があり、どの形式を選ぶかによって費用も供養方法も変わります。
それぞれの特徴と費用感を整理しておきましょう。
1. 合祀(ごうし)型
他の方と一緒に納骨される形式です。最も費用を抑えられ、5万円〜20万円前後が相場です。
一度合祀するとお骨の取り出しはできませんが、お寺が永代にわたり供養してくれる安心感があります。
2. 個別型
一定期間は個別の区画で納骨し、期間終了後に合祀する形式です。20万円〜50万円前後が目安で、プライベートな空間を保ちながら供養を受けたい方に向いています。
3. 納骨堂型
屋内の施設にお骨を安置する方法です。天候に左右されず、アクセスもしやすいのが特徴。30万円〜70万円前後が一般的です。
4. 樹木葬型
墓石の代わりに樹木を墓標とする自然葬の一種で、20万円〜50万円前後が目安。環境への配慮や自然との共生を大切にする方に選ばれています。
いずれの形式でも、管理料が発生しない仕組みを選んでおくと、長期的な安心につながります。管理料がかかる場合でも、「支払いを行う方が亡くなった後、合祀墓に移して供養を続けてくれる」など、柔軟な対応をしてくれるお寺を選ぶことが大事です。
永代供養の費用は“安さ”よりも“将来の安心”を基準に選ぶことが、後悔しない選び方です。
▶︎3. 永代供養における「管理料」の重要性

3.1 管理料が発生する永代供養のリスク
永代供養は「お墓を継ぐ方がいない人のための供養方法」です。にもかかわらず、管理料が発生するタイプの永代供養を選んでしまうと、将来的にトラブルになる可能性があります。
管理料とは、お墓や納骨堂の維持管理のために定期的に支払う費用です。一般的な墓地では毎年1万円〜数万円ほどかかることもあります。永代供養においても、この管理料が継続的に必要な契約内容になっている場合があります。
しかし、支払いを行う本人が亡くなった場合、その後の支払いが滞ることも少なくありません。管理料が未払いになると、供養の継続やお骨の保管に影響が出るケースもあります。
つまり、「永代」と名がついていても、実際には半永久的ではない場合があるのです。
また、契約時に「管理料込み」と思っていたら、後になって追加の支払いが必要になる例も見られます。金額の大小にかかわらず、契約内容を曖昧にしたまま進めると、後々トラブルの原因になりかねません。
永代供養を選ぶ際は、「契約後に管理料が発生しないか」を最初に確認することが何より重要です。
3.2 管理料が不要な永代供養を選ぶメリット
管理料が不要な永代供養は、金銭面でも精神面でも安心できる供養の形です。初回に費用を一括で納めれば、その後の負担がなく、お寺が永続的に供養と管理を引き継いでくれます。
主なメリットは次の通りです。
将来的な金銭トラブルを防げる
後継者がいなくても、供養が継続的に行われる
家族に支払いの負担を残さない
契約内容がシンプルで、将来の見通しが立てやすい
特に、身寄りのない方や、将来的に支払いを引き継ぐ人がいない場合には、管理料不要の永代供養を選ぶことで安心感が大きく高まります。
また、永代供養を提供している寺院の中には、管理料がかからないうえに、お盆・お彼岸・回忌法要などの供養をお寺側で行ってくれるところもあります。
供養に行けなくても、心を込めた法要が続いていく仕組みがあれば、亡くなられた方も安らかに見守られるでしょう。
3.3 万一のときに安心な「合祀墓」での供養
永代供養では、遺骨を複数人で一緒に納める「合祀(ごうし)墓」という形式がよく用いられます。合祀墓は、費用面・供養面の両方でバランスが取れた方法として選ばれています。
合祀墓では、納骨後にお骨を他の方と同じお墓にまとめて安置します。そのため、個別墓のように区画を維持する必要がなく、管理料が不要で長期にわたり供養が続くのが大きな特徴です。
この形式では、次のような安心感があります。
管理費や維持費の心配がない
後継者がいなくても、お寺が供養を続けてくれる
合祀後も、お盆やお彼岸などにお寺が読経や法要を行ってくれる
特に、お寺が責任を持って供養を続けてくれる合祀墓であれば、家族に負担をかけず、長期的な安定供養が可能です。
「お墓を守る人がいなくても、供養は途絶えない」――それを実現できるのが、管理料不要の永代供養と、しっかりと整備された合祀墓の仕組みです。
永代供養を選ぶときは、“管理料が発生しないか”“合祀後の供養体制が整っているか”を必ず確認することが大切です。
▶︎4. 永代供養を選ぶ際の注意点とよくある失敗例
4.1 費用の安さだけで選んでしまう
永代供養を検討する際、つい「できるだけ費用を抑えたい」と考えてしまうものです。ですが、費用の安さだけで選ぶと、後になって後悔するケースが少なくありません。
たとえば、初回の費用は安く見えても、実際には「納骨料」「永代供養料」「管理料」が別途必要になる場合があります。費用の一部しか表示していないプランもあるため、契約後に追加費用が発生してしまうことも。
また、あまりに安い永代供養では、供養の回数や内容が限定されていることもあります。
供養は金額よりも「どんな形で供養してもらえるか」が大切です。
永代供養を選ぶ際は、
初回費用に何が含まれているのか
管理料は発生しないか
合祀後もお寺が供養を続けてくれるか
この3点をしっかり確認しておきましょう。
費用の安さよりも「安心して任せられるか」を基準にすることが、後悔しない選び方です。
4.2 契約後に追加費用が発生する
永代供養では、契約時に明示されていない費用が後から発生するケースもあります。
特に注意したいのが、次のような項目です。
法要や読経の際に別途お布施が必要
合祀までの期間中、個別保管料が発生する
刻字料や銘板設置費用が別料金
管理料が「年単位」で発生する
これらの費用は、契約時にしっかり説明を受けないと見落としやすい部分です。
実際、管理料が年ごとに必要な契約では、支払いをしていた方が亡くなった時点で管理が止まってしまうこともあります。
トラブルを防ぐためには、契約書や見積書を必ず確認し、費用の内訳を明確にしておくことが重要です。
「費用総額」と「今後一切の管理料がかからないか」を確認することで、安心して永代供養を任せられます。
4.3 法要や供養内容の確認不足で後悔
永代供養を契約する際にもう一つ多いのが、供養の内容を十分に確認しないまま契約してしまう失敗です。
永代供養は、単にお骨を納めるだけではなく、その後の供養がどう行われるかが大切なポイントです。
たとえば、
お盆やお彼岸に法要を行ってくれるか
年忌法要(回忌供養)は含まれているか
合祀後もお寺が読経を続けてくれるか
これらを確認せずに契約すると、「思っていた供養がされていない」と感じてしまうことがあります。
お寺によっては、お盆やお彼岸の法要を定期的に執り行い、ご遺族が参列できなくても心を込めて供養を続けてくれるところもあります。
そうしたお寺を選ぶことで、離れていても安心して供養をお任せできます。
永代供養は、「誰が」「どのように」「いつ」供養してくれるかが信頼の鍵です。
契約前に供養の内容を具体的に確認し、納得したうえで選ぶことが大切です。
永代供養は“契約して終わり”ではなく、“長く安心して供養が続くか”を見極めることが大事です。
▶︎5. 曹洞宗迎福寺の永代供養について
5.1 曹洞宗の教えに基づく永代供養の考え方
千葉県印西市にある曹洞宗 天長山 迎福寺は、今から約518年前、底芝誾才(ていしぎんさい)大和尚によって開かれた、500年以上の歴史を持つ曹洞宗の禅寺です。
開祖・道元禅師の「只管打坐(しかんたざ)」の精神を大切にし、地域と共に歩みながら、人々の心に寄り添う供養を続けています。
曹洞宗の教えでは、「仏の心は誰の中にも宿る」とされています。迎福寺の永代供養もその理念のもと、すべての方の安寧を祈り、世代を超えて供養を絶やさないことを大切にしています。
現住職である三十一世・慈孝宗禎和尚は、
「寺院とは地域の方々と共に生き、ご先祖を敬い、仏道を共に考える場所である」
という考えを掲げ、現代に合った形で供養のあり方を提案しています。
そのため、迎福寺の永代供養は単なる納骨の場ではなく、“心をつなぐ供養の場”としての役割を担っています。
5.2 管理料不要で安心できる迎福寺の永代供養
迎福寺では、時代の変化に合わせて管理料不要の永代供養を行っています。
お墓を継ぐ方がいない方や、将来的な費用負担に不安を感じている方でも安心して任せられるように配慮されています。
永代供養墓「慈光の郷(じこうのさと)」は、観音菩薩と地蔵菩薩が見守る静かな境内に設けられ、三十三回忌までお寺が責任を持って供養を行う仕組みです。
永代供養の費用は30万円(永代供養のみの場合)で、年間管理料は一切かかりません。
また、合祀墓を希望される場合は5万円(墓誌への刻字あり)で利用でき、経済的にも負担が少なく、誰もが安らかに眠れる環境が整えられています。
迎福寺の永代供養が信頼されている理由は、
契約後に追加の管理料が一切不要
寺院が三十三回忌まで責任をもって供養
観音菩薩と地蔵菩薩が見守る静かな供養環境
これらの安心がそろっているからです。
「供養を絶やさず、お金の心配もいらない」――それが迎福寺の永代供養の最大の魅力です。
5.3 お盆・お彼岸・回忌法要まで丁寧に行う迎福寺の供養
迎福寺では、永代供養のご遺骨をただ安置するだけでなく、お盆・お彼岸・回忌法要など、季節ごとの供養を丁寧に執り行うことを大切にしています。
年間を通して、次のような法要が行われています。
1月:元旦修正会(しゅしょうえ)祈祷
3月:春彼岸会
6月:大般若祈祷法要
8月:盂蘭盆会・大施餓鬼会
9月:秋彼岸会
10月:羽黒山例祭
これらの法要では、迎福寺の僧侶が心を込めて読経し、ご先祖や故人を供養します。参列できない方のためにも、お寺側がすべての供養を継続して行う体制が整っており、遠方に住む方や高齢の方にも安心です。
また、葬儀や法要の際は複数の僧侶が厳かに読経し、すべての費用について事前に見積もり・領収書を発行するなど、透明性の高い運営を行っています。
ご寄進の強要もなく、どなたでも安心して相談できる開かれた寺院として地域から信頼を得ています。
迎福寺では、永代供養を通して「誰もが穏やかに供養される社会」を目指しています。
三十三回忌まで続く祈りと、管理料不要の安心設計――それが迎福寺の永代供養の真心です。
▶︎6. まとめ:費用相場を理解して安心の永代供養を選ぶために
6.1 永代供養選びで後悔しないための3つの確認ポイント
永代供養は、「お墓を継ぐ方がいない」「将来の費用負担を減らしたい」という方にとって、とても安心できる供養の方法です。
しかし、その一方で、契約内容をよく確認せずに選んでしまうと、思わぬトラブルや後悔につながることもあります。
後悔しないためには、次の3つのポイントを必ず確認しておきましょう。
管理料が発生しないかどうか
永代供養は継承者のいない方のための供養です。管理料が発生するタイプでは、支払いを行っていた方が亡くなった後、供養が途絶えてしまう可能性があります。契約前に「管理料が不要」であることを明確に確認しましょう。
供養内容と期間を把握しておく
永代供養では、お寺によって供養の回数や期間(例:三十三回忌まで)が異なります。読経・法要の頻度や、合祀までの流れを具体的に確認することが大切です。
お寺が信頼できるかどうか
契約の安心感だけでなく、「供養を丁寧に行ってくれるお寺かどうか」も大切です。
お盆・お彼岸など、年間を通じて供養を続けてくれる寺院であれば、故人も穏やかに見守られるでしょう。
永代供養は一度契約すると長く続く供養です。だからこそ、金額よりも「永く安心して任せられるか」で選ぶことが、後悔しないための最大のポイントです。
6.2 心を込めた供養をお寺に任せる安心感
永代供養は、単に「費用を抑える」ための方法ではありません。
大切な方の供養を、信頼できるお寺に託し、長く見守ってもらうための選択です。
特に、曹洞宗迎福寺のように、管理料が不要で、三十三回忌まで丁寧に供養を続けてくれる寺院では、後継者がいなくても安心して任せられます。
お盆やお彼岸、回忌法要まで一つひとつ丁寧に執り行う姿勢は、「供養が生き方に寄り添う」という曹洞宗の教えそのものです。
現代社会では、核家族化や少子化の影響で、お墓を継ぐ文化が変わりつつあります。
そんな中で、永代供養は新しい形の“安心”をもたらしてくれる存在です。
費用の相場を理解し、信頼できるお寺に託すことで、金銭的にも心情的にも安らぎを得られるはずです。
永代供養は、「供養の不安」を「安心の祈り」に変える選択。心を込めた供養をお寺に任せ、穏やかな未来を迎えましょう。
▶︎管理料不要の永代供養なら迎福寺にお任せください
迎福寺では、観音菩薩と地蔵菩薩に見守られた「慈光の郷」永代供養墓をご用意しています。
お寺が三十三回忌まで責任を持って供養を行うため、後継者がいない方や費用面の不安がある方にも安心です。追加の管理料は一切不要です。
永代供養や合祀墓に関する詳細は、迎福寺ホームページの「墓地について」をご覧ください。

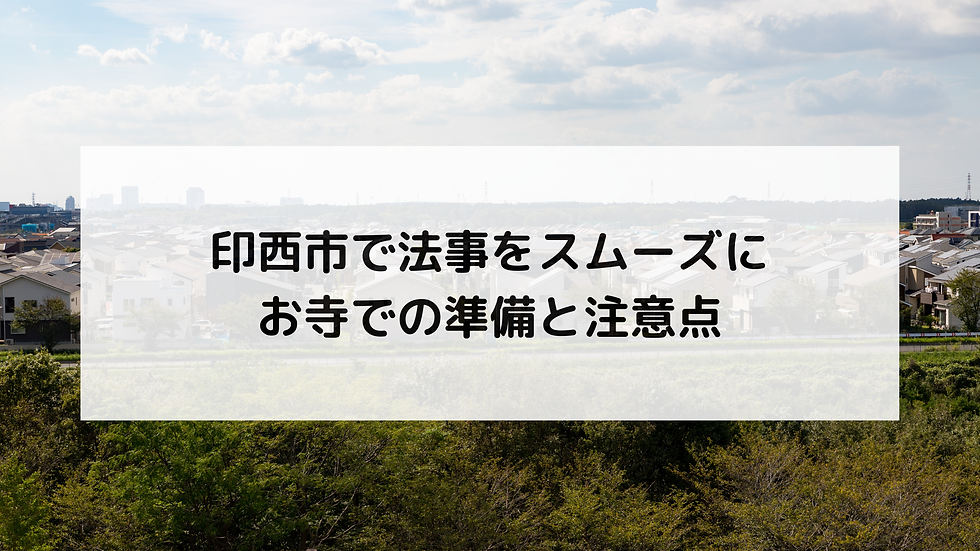

コメント