法事をまとめて一度に済ませたい方へ|時期と注意点を完全ガイド
- 宗教法人迎福寺
- 2025年4月22日
- 読了時間: 13分

▶︎1. 法事をまとめて行うってどういうこと?

1.1 法事と法要のちがいとは?
「法事」と「法要」って、なんとなく使い分けていませんか?実はこのふたつ、意味が少し違うんです。
「法要」は、亡くなった方の冥福を祈るためにお経をあげる仏教の儀式のこと。僧侶にお勤めしていただく場面ですね。 一方で「法事」は、その法要にくわえて、親族が集まって食事をしたり、故人を偲んだりする一連の流れ全体を指しています。
たとえば、「一周忌の法事をした」というときは、
僧侶による読経(法要)
その後の会食や引き出物の用意(法事全体)
こういった流れが含まれているんです。 つまり、「法要」は儀式そのもの、「法事」は儀式を含んだイベントのようなもの、と考えるとわかりやすいですよ。
1.2 「法事をまとめて」とは何をまとめるの?
「法事をまとめて行う」って、実はそんなに特別なことではないんですよ。
昔は命日ごとに法要を行うのが一般的でしたが、今は事情が変わってきました。
たとえばこんなケース、聞いたことありませんか?
一周忌と三回忌を一緒に
三回忌と七回忌を同時に
兄弟のお墓参りを同日にまとめて
こういったように、「本来なら別々に行う法要を、一度にまとめておこなう」ことを指しているんです。
実際には、
一人の故人に対して複数の年忌法要をまとめる
複数の故人に対する法要を一緒に行う
このどちらの意味でも使われることがあります。 どちらにしても、忙しい現代に合わせて少しでも負担を減らす工夫のひとつなんです。
1.3 昔と今で変わってきた法事のスタイル
今の時代、法事のかたちはどんどん変わってきています。
昔は、親族が近くに住んでいて、年に何度もお寺に集まるのが当たり前でした。
でも今はどうでしょうか?
遠方に住んでいて集まるのが大変
共働きや高齢の親族が増えている
仏教に詳しい人が少なくなっている
こういった理由から、「できるだけシンプルに」「でも丁寧に」というニーズが高まっているんです。
法事をまとめて行うのは、こうした現代のライフスタイルに合わせた、新しい供養のかたちとも言えます。 もちろん、「まとめる」ことに対して不安な気持ちを持つ方もいらっしゃいますが、大切なのは気持ちを込めて供養することなんですよ。
▶︎2. 法事をまとめて行う主な理由とタイミング

2.1 遠方の親族が集まりやすいから
「また来年も?」「また有休取らなきゃ…」そう感じる方が増えているのが現実です。
現代の家族は、かつてのように同じ地域にまとまって暮らしているわけではありません。
兄弟姉妹がそれぞれ別の県に住んでいたり、海外勤務中だったりすることも珍しくないですよね。
法事をきちんと行いたい気持ちはあっても、現実には、
毎年法事のために長距離移動するのが大変
小さな子どもを連れての移動は負担が大きい
有給休暇やスケジュールの調整が難しい
そんな理由から、「一度で済ませられるなら、そのほうが助かる」という声が増えているんです。
とくに多いのは、一周忌と三回忌を一緒に行うパターン。 「去年はコロナで集まれなかったから…」といった事情で、数年分をあわせて行う方もいらっしゃいます。
親族が一度に集まれる貴重な機会を活かして、心のこもった供養ができれば、それで十分なんです。
2.2 経済的・時間的な負担を減らすため
法事を行うには、想像以上に「お金」と「時間」がかかるものなんです。
たとえば、一度の法事でかかる主な費用を挙げてみましょう。
僧侶へのお布施(3万円~5万円程度)
会場使用料(お寺または斎場)
仕出し料理や会食代(1人5000円~1万円)
引き出物(1セット2000円~5000円)
お花代・飾りつけ・送迎費 など
これだけ見ても、10万~20万円近くかかることも珍しくありません。 それを年に何度も行うとなると、家計への負担はかなりのもの。
さらに、準備や手配にも時間がかかります。
親族への連絡・出欠確認
会場や仕出しの予約
お寺との日程調整
引き出物の選定と手配
仕事や家事、育児に追われていると、これらを毎回こなすのは本当に大変。 そんな背景もあって、「どうせやるなら、まとめて効率よく」という考えが広まっているんです。
もちろん、効率だけを求めるのではなく、きちんと気持ちを込めて供養できるように、バランスをとることが大切ですよ。
2.3 菩提寺や僧侶との都合が合わないとき
「お坊さんの都合がつかなくて日程をずらす」…実はよくあることなんです。
お寺も現代では人手不足が進んでいます。住職一人で複数のお檀家を回っているケースもあり、
希望の日に読経をお願いできない
法事の希望が集中する時期はすぐ埋まってしまう
お彼岸やお盆前後しか動けないこともある
こういった状況がよく起きています。
さらに、最近は菩提寺を持たずに「必要なときだけ読経を依頼する」というケースも増えてきました。 この場合、手配できる僧侶の人数が限られていたり、出張の費用がかかったりして、どうしても日程が限られてしまうんです。
そんなとき、お寺や僧侶から「今回は2つの法要を一緒に行っても問題ありませんよ」と提案されることも。
供養の気持ちが大事だからこそ、お寺側と協力して無理のない方法を選ぶことがとても大事なんです。
2.4 まとめて行うタイミングの選び方
法事をまとめて行うと決めたら、「いつにするか」が大切なポイントです。
できるだけ節目を大切にしつつ、親族の集まりやすさも考慮して決めたいですよね。
実際によく選ばれるタイミングはこちらです。
タイミング | 特徴や理由 |
一周忌・三回忌などの年忌 | 大きな節目なので、他の法要とまとめても違和感が少ない |
お盆・お彼岸の時期 | 供養のタイミングとして自然で、みんなの予定も調整しやすい |
命日が近い複数の故人がいるとき | 一緒に供養することで、移動や準備の手間も最小限に抑えられる |
納骨やお墓参りのついで | 現地に行くタイミングにあわせて法要も行えるので効率が良い |
たとえば、こんなケースもあります。
「祖父の三回忌に合わせて、昨年できなかった祖母の一周忌も一緒に行いました。 遠方から来る叔父たちも『助かったよ』と言ってくれて、無理なく気持ちよく供養できました。」
このように、柔軟な対応が求められる今だからこそ、タイミングを工夫することで“心ある供養”が実現できるんです。
無理に慣習に縛られず、家族やお寺と話し合って、自分たちに合ったタイミングを選ぶことが大切ですね。
▶︎3. 法事をまとめて行うときの準備と流れ

3.1 どの法要をまとめられるの?
実は、ほとんどの年忌法要はまとめて行うことができるんです。
たとえば、
一周忌と三回忌を一緒に
三回忌と七回忌を同時に
亡くなったご両親や兄弟姉妹の法要を一日で
といった組み合わせがよく見られます。
もちろん、法要をまとめるときは、お寺の意向や家族の希望にも配慮が必要です。 仏教的には、年忌ごとの法要にはそれぞれ意味がありますが、供養の気持ちがこもっていれば同時に行っても問題はないとされています。
宗派やお寺によって考え方が異なる場合もあるので、まずは一度相談してみるのが安心ですよ。
3.2 お寺への相談と打ち合わせのポイント
まとめて法事を行うときは、早めの相談が何より大事です。
お寺に相談するときに伝えておきたいポイントはこちらです。
まとめたい法要の内容(例:三回忌と七回忌)
供養する人数や故人の関係性
希望の日程や会場(自宅か、寺院か、会館か)
参加予定の人数
お寺によっては、会食の手配や引き出物の準備も任せられることがあります。
事前に確認しておけば、当日の段取りもスムーズに進みますよ。
また、僧侶へのお布施や必要な準備物もあわせて確認しておくと安心です。 不明点はどんどん聞いて大丈夫。わからないまま進めないようにすることが大切です。
3.3 お布施・会食・引き出物の準備
複数の法要をまとめるときは、金額や手配のしかたにも工夫が必要です。
たとえばお布施について。 複数の法要を一緒にするからといって、金額が倍になるわけではありません。 ただし、お寺との関係性や内容によって異なるので、目安を確認してから包むようにしましょう。
また、会食や引き出物も以下の点を意識するとスムーズです。
会食は「通夜ぶるまい」程度の簡易な形式にする方が増えています
お膳ではなく、仕出し弁当を持ち帰りにするケースも
引き出物は人数分で十分。高価すぎず実用的な品が好まれます
まとめて行うことで一つひとつの準備を簡素化できるので、負担が少なくなるんです。
3.4 服装やマナーはどうする?
法事の服装やマナーは、基本を押さえておけば心配いりません。
まず服装ですが、まとめて行う場合でも法事であることには変わりません。 基本は「喪服」または「黒・紺・グレーなどの控えめな服装」で問題ありません。
とくに気をつけたいのが以下のポイントです。
女性はアクセサリーを控え、肌の露出が少ないものを
子どもが参加する場合は、制服や落ち着いた色味の服で
香水や派手なネイルは避ける
また、法事の場では、
故人への黙とうや焼香の流れ
僧侶への挨拶や感謝の言葉
会食時の配慮や気遣い
など、小さなマナーが集まって場の雰囲気が整います。 大切なのは形式よりも「心をこめること」です。
3.5 実際の1日の流れのイメージ
まとめて行う法事は、想像以上にスムーズなんですよ。
たとえば、よくある1日の流れはこちらです。
時間帯 | 内容 |
10:00 | 寺院や会場に集合・僧侶とご挨拶 |
10:30〜11:30 | 法要(複数の年忌をあわせてお勤め) |
11:30〜12:00 | お墓参りや納骨など(希望に応じて) |
12:00〜13:00 | 会食または持ち帰りのお弁当配布 |
13:00 | 解散・お礼のあいさつと引き出物のお渡し |
このように、半日あればしっかり供養ができて、遠方の方も帰宅しやすいスケジュールになります。
迎福寺のように、法要から会食・納骨まで一括で相談できるお寺なら、流れも整理しやすく安心なんですよ。
▶︎4. 法事をまとめて行うメリット・デメリット
4.1 メリット:親族の負担が減る
いちばんのメリットは、親族の精神的・身体的な負担が軽くなることです。
法事のたびに遠方から足を運んだり、準備に追われたり…。 とくに高齢の方や、小さなお子さんがいるご家族にとっては、毎回の参加は正直つらいですよね。
まとめて法事を行うことで、
移動が1回で済む
挨拶や準備が簡略化できる
気持ちの切り替えがしやすくなる
といった実感があるようです。
「一度に心を込めて供養できて、気持ちにも区切りがつきました」と感じる方も多いんですよ。
4.2 メリット:日程調整がしやすい
家族やお寺のスケジュールを合わせやすいのも、大きな利点です。
特定の命日ごとに法要を行う場合、その日が平日だったり、ほかの予定と重なってしまうことも多いですよね。
まとめて行えば、
みんなの都合のよい日を選べる
季節や天気を考慮して日程を調整できる
会場の予約や僧侶の手配もしやすくなる
というメリットがあります。
お盆やお彼岸、三連休などをうまく活用すれば、親戚同士の再会もゆっくり楽しめますよ。
4.3 デメリット:供養の意味が薄れる?
一方で、「まとめると形式的になってしまうのでは?」という不安の声もあります。
たしかに、本来の年忌法要はひとつひとつに意味があります。 それを省略することに、抵抗を感じる方がいるのも自然なことです。
とくにご年配の親族や、昔からのしきたりを大切にする地域では、
「手抜きに見える」
「気持ちがこもっていないと思われる」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
大切なのは、どう行うかではなく、どんな気持ちで供養するかです。 事前に親族でよく話し合い、理解を得ることが何より大事なんですよ。
4.4 トラブルを防ぐために気をつけたいこと
法事をまとめて行うときに、ちょっとした気配りがトラブルを防いでくれます。
こんな点に気をつけてみてください。
【親族への事前説明】なぜまとめるのか、どの法要を行うのかを丁寧に伝える
【人数の把握】参加者を事前に確認して、会食や引き出物の数を調整する
【お布施の金額】まとめるからといって大幅に減らすと失礼に見えることも
【香典の扱い】複数の供養がある場合、受付方法や名簿整理にも配慮を
ちょっとした準備で、当日の空気がぐんと和らぎますよ。
4.5 こんな人には「まとめて法事」が向いてます
まとめて法事を行うのに向いているのは、こんな方たちです。
遠方に住んでいて毎年帰省するのが難しい
高齢や病気などで外出が大変な親族が多い
少人数の家族で準備に不安がある
お寺との付き合いが浅く、段取りがよくわからない
忙しくても、丁寧な供養をしたいと考えている
当てはまる方は、無理のない形で供養を行う手段として、まとめて法事を選ぶのもおすすめですよ。
▶︎5. まとめ:現代に合った供養のかたち
5.1 無理なく、心をこめて供養するために
法事をまとめて行うことは、現代ならではの柔軟な供養のかたちです。
昔のように、毎年きっちりと命日に法要を営むのが難しい…という方は今、とても増えています。 共働き世帯の増加や、遠方に住む家族の存在、介護や体調など、現実的な事情がたくさんありますよね。
だからといって、「供養の気持ちが薄れた」と思う必要はありません。 大切なのは、「気持ちを込めて、故人を思い、手を合わせること」。
法事をまとめて行うことは、
親族への負担を減らす
日程や準備をスムーズにする
心穏やかに供養に向き合える時間をつくる
そんな前向きな選択でもあるんです。
一人ひとりの状況に合わせた、無理のない方法で。 それでも、手を合わせる気持ちはちゃんと届いていますよ。
5.2 法事の相談は迎福寺へ
もし、法事のことでお悩みやご不安があれば、千葉県印西市の「曹洞宗 天長山 迎福寺」へぜひご相談ください。
迎福寺は、今から518年前に開かれた由緒あるお寺です。 印旛沼の自然に囲まれた静かな環境の中で、心を込めた仏事を行っています。
こんな特徴があるんですよ。
法要や葬儀をご要望に応じて柔軟に対応(通夜葬儀、一日葬など)
宗派を問わず、どなたでもご相談いただけます
ご高齢の方や体の不自由な方にもやさしい椅子席の本堂
事前のお見積り・明朗な費用提示・領収書の発行で安心
少人数の法要にも対応し、送迎車の手配も可能
引き出物や供花、お料理も低価格で手配可能
また、「生活保護を受けている方」「仏事費用にお悩みの方」にも、分け隔てなく真心を込めたご対応をされているのが、迎福寺の大きな魅力です。
「法事の進め方がわからない」「まとめて供養しても大丈夫?」
そんな疑問も、住職が丁寧に対応してくださいますよ。
無理なく、でも心を込めて。 そんな現代の供養に、迎福寺はやさしく寄り添ってくれます。
▶︎法事をまとめて行いたいなら、迎福寺へご相談ください
「遠方の親族がなかなか集まれない」「毎年の法事の準備が大変」
そんなお悩みをお持ちの方にこそ、迎福寺の“心を込めた柔軟な法事対応”がおすすめです。
千葉県印西市にある曹洞宗 天長山 迎福寺では、 ご家族の事情に合わせた法事の進め方を、丁寧にご提案しています。
年忌法要を一緒にまとめたい
小規模でもきちんと供養をしたい
料金や準備について不安がある
こんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
事前のお見積り・明確な費用提示・送迎のご相談も可能です。
法事のことは、地域に寄り添い続ける迎福寺におまかせしてみませんか?

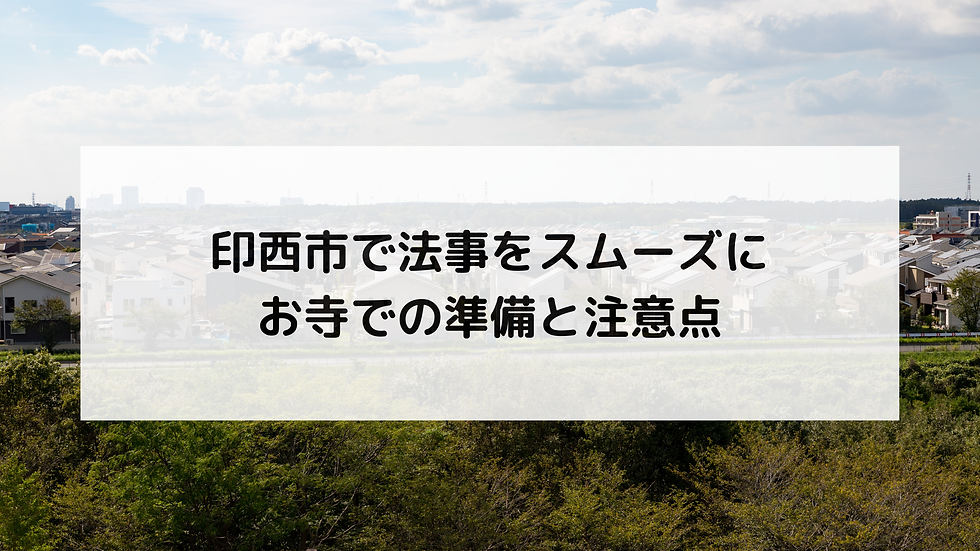

コメント