生活保護者の仏事費用を安心サポート|補助金の仕組みと流れ
- 宗教法人迎福寺
- 2025年9月2日
- 読了時間: 16分

▶︎1. 生活保護で利用できる仏事の費用補助について

1.1 葬祭扶助制度の基本内容
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬儀を執り行うための費用を公的に支援してもらえる制度があります。これを「葬祭扶助」と呼びます。生活保護法第18条に基づき、最低限の葬儀が行えるように自治体が費用を負担してくれる仕組みです。
支給の対象となるのは、故人が生活保護受給者であった場合や、葬儀を行う親族が生活保護を受けている場合などです。申請が認められれば、葬儀社を通じて必要な費用が直接支払われます。
葬祭扶助でカバーできる範囲は、主に以下の通りです。
火葬にかかる費用
棺や骨壺など最低限必要な物品
遺体搬送や保管にかかる費用
一方で、通夜や告別式、僧侶による読経や戒名料などは含まれません。あくまで「最低限のお見送り」を支える制度であることを理解しておくことが大事です。
生活保護を受けている方でも dignified(尊厳ある)形で最期を迎えられるよう、公的な支援が用意されているのです。
1.2 生活保護で葬祭扶助を利用できる条件
葬祭扶助を利用できるのは、誰でもというわけではありません。いくつかの条件を満たす必要があります。ここを理解しておかないと、せっかく制度があるのに申請が却下されてしまうこともあります。
主な条件は次の通りです。
故人が生活保護を受けていた場合
喪主となる親族が生活保護を受けている場合
故人に経済的に扶養できる親族がいない、または扶養が難しい場合
さらに大事なのが、葬儀を行う前に自治体へ申請をすることです。葬祭扶助は事後申請が認められないため、葬儀を済ませてから申請しても補助は受けられません。
よくある失敗例としては、
亡くなった直後に慌てて葬儀社と契約してしまう
親族が「自分で払える」と誤解し、結果的に支払いが困難になる
役所に相談せずに進めてしまい、申請できるはずの葬祭扶助を逃す
といったケースがあります。これを避けるためには、必ず葬儀前に役所へ相談することが欠かせません。
葬祭扶助を受けることで、費用の不安を軽減しつつ、安心して故人を送り出す準備ができます。
1.3 葬祭扶助の申請から利用までの流れ
葬祭扶助を利用するには、一定の手順を踏む必要があります。流れを理解しておくと、いざという時に慌てずに対応できます。
一般的な流れは以下の通りです。
役所の生活保護担当課へ連絡
まずは故人が亡くなったことを役所に伝えます。この時点で葬祭扶助を利用したい意思を相談します。
申請書類の提出
喪主になる方が申請書を記入し、必要に応じて死亡診断書や身分証明書などを提出します。葬儀社が代行してくれる場合もあります。
役所による審査
故人や喪主が生活保護受給者であるか、経済的に困難な状況かを確認されます。扶養可能な親族がいるかどうかも判断材料になります。
葬祭扶助の決定通知
条件を満たしていれば、役所から葬祭扶助が支給される旨の通知が届きます。
葬儀の実施と費用の支払い
支給が決定すると、葬儀社に対して自治体から直接費用が支払われます。喪主が一時的に立て替える必要はありません。
注意点として、申請前に葬儀を進めてしまうと補助が受けられないことがあります。また、自治体ごとに必要書類や審査基準に細かな違いがあるため、事前確認が大切です。
手続きを正しく踏むことで、生活保護を受けていても安心して葬儀を行える環境が整います。
▶︎2. 生活保護で賄える仏事の費用と対象範囲

2.1 成人と子どもで異なる支給額の目安(当山付近では20万円前後が一般的)
葬祭扶助で支給される金額は全国一律ではなく、自治体ごとに上限が定められています。一般的には成人と子どもで金額が分かれており、成人の場合は20万円前後、子どもの場合は16万円前後が目安となっています。
当山付近の地域でも、支給額はおおよそ20万円前後であり、多くのケースでは直葬(火葬のみ)に必要な費用をまかなえる範囲に収まります。自治体によっては21万円を上限とするところもあり、少しずつ差があります。
ここで気をつけたいのは、支給される金額が「上限」であるという点です。必ずしも全額が支給されるわけではなく、葬儀にかかる実際の費用が基準額より低ければ、その金額分しか支給されません。
よくある失敗としては、
支給額の範囲を超える葬儀プランを選んでしまい、自己負担が発生する
地域による上限額の違いを調べずに手続きを進め、想定より補助が少なかった
子どもの場合の支給額を知らずに成人と同じと考えてしまい、金額にズレが生じた
こうしたトラブルを避けるためには、事前に自治体へ確認し、予算の目安を把握しておくことが大事です。補助金の範囲を理解しておくことで、金銭的な不安を減らし、安心して葬儀を進められます。
2.2 一般的な葬儀との違いと直葬の形式
葬祭扶助で行える葬儀は、一般的な葬儀とは大きく異なります。補助の対象となるのは直葬(火葬のみを行う形式)であり、通夜や告別式といった儀式は含まれません。
一般的な葬儀では、通夜・告別式・僧侶による読経・戒名の授与・会食(精進落とし)など、さまざまな流れがあります。その分、費用は数十万円から百万円単位に及ぶことも珍しくありません。
一方で、葬祭扶助で行う直葬は、火葬を中心とした最小限の内容にとどまります。具体的には、以下のような流れです。
ご遺体の搬送
棺や骨壺の準備
火葬手続き
火葬・収骨
この形式であれば、20万円前後の補助金で十分に費用をまかなえます。
ただし、直葬には次のような注意点もあります。
通夜や告別式がないため、親族や友人とゆっくり故人を偲ぶ時間を持てない
僧侶による読経や戒名が含まれないため、宗教的な儀式を重視する場合には不十分と感じることがある
火葬場の空き状況によっては希望する日時に実施できない場合がある
直葬は費用を抑えることができますが、送り方としてどのような形が望ましいのかを家族でしっかり話し合っておくことが大切です。
費用面の負担を軽減しながらも、故人を大切に見送る気持ちを忘れないことが何より大事です。
2.3 葬祭扶助では対象外となる費用項目
葬祭扶助は「最低限の葬儀費用」を支援する制度のため、すべての費用をまかなえるわけではありません。対象外となる項目を理解していないと、思わぬ自己負担が発生することがあります。
代表的に補助の対象外となるのは次のようなものです。
僧侶へのお布施(読経料や戒名料)
通夜・告別式の費用(式場使用料や設営費)
会食費(通夜振る舞い・精進落とし)
香典返しや礼状などの返礼品
会葬御礼や案内状の印刷費用
花祭壇や装飾に関する費用
これらは遺族の希望に応じて追加で行うものであり、葬祭扶助の支給額には含まれません。
よくある失敗例としては、
僧侶へのお布施が含まれると勘違いし、後から予算オーバーになる
家族葬を想定して準備を進めたが、実際は直葬しか補助対象にならず自己負担が増えた
香典返しや供花を手配してしまい、想定以上の出費につながった
こうしたトラブルを防ぐためには、「何が補助されて、何が自己負担になるのか」を事前に明確にしておくことが重要です。
特に宗教的な儀式を大切にしたい場合は、追加費用が必要になることを理解し、葬祭扶助と自己負担分のバランスを考えて計画を立てると安心です。
▶︎3. 生活保護以外で利用できる仏事費用の補助制度

3.1 社会保険から支給される埋葬料や葬祭費
生活保護を受けている方でも、加入していた社会保険の制度から埋葬料や葬祭費が支給される場合があります。これは生活保護の葬祭扶助とは別の制度で、重複して受け取れることもあるため、知っておくと大きな助けになります。
主な制度は次の通りです。
健康保険(協会けんぽや組合健保など)
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行う遺族に「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。金額は5万円程度が一般的です。
国民健康保険
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合も、葬儀を行った遺族に「葬祭費」として3万円〜7万円程度が支給されます。自治体によって差があります。
共済組合
公務員などが加入する共済組合では、葬祭費用として5万円〜10万円程度が支給される場合があります。
これらの制度は、申請しないと受け取れません。よくある失敗例として、
生活保護を受けているから葬祭扶助だけだと思い込み、社会保険からの給付を申請しなかった
故人が国民健康保険か社会保険かを確認せず、結果的に手続きを逃してしまった
支給額が自治体によって異なることを知らず、想定より少なかった
というケースがあります。
生活保護の葬祭扶助だけでなく、健康保険や共済組合の給付も確認することで、さらに費用負担を軽減できる可能性があります。
3.2 自治体が提供する市民葬などの仕組み
生活保護の葬祭扶助以外にも、自治体によっては独自の仕組みとして「市民葬」や「区民葬」と呼ばれる低価格の葬儀プランを提供している場合があります。これは生活保護を受けていない方でも利用でき、費用を抑えたいご家族にとって大きな助けとなります。
市民葬の特徴は以下の通りです。
葬儀社と自治体が提携し、一定の低価格プランを設定している
直葬から小規模な家族葬まで対応できることが多い
棺や骨壺、霊柩車など基本的な内容が含まれる
市民であることを証明できれば利用可能(住民票や身分証の提示が必要)
費用は地域によって差がありますが、一般的には10万円〜30万円程度で利用できます。通常の葬儀費用に比べると大幅に抑えられるため、経済的に余裕のない家庭には心強い制度です。
よくある注意点としては、
市民葬を希望しても、提携していない葬儀社に依頼してしまい、割引が適用されなかった
市民葬の基本プランには含まれていないサービス(花祭壇や会食)を追加し、結果的に費用が高くなってしまった
利用条件(住民票の有無など)を確認しておらず、当日になって使えなかった
という失敗が挙げられます。
生活保護を受けていなくても、自治体の市民葬を活用すれば、費用を大きく抑えつつ dignified(尊厳ある)形でお見送りが可能です。
▶︎4. 生活保護を受けている場合の香典と仏事費用の関係
4.1 葬祭扶助利用時に香典は没収されるのか
生活保護を受けている方の葬儀で気になる点のひとつが、香典の扱いです。 「葬祭扶助を利用した場合、香典は没収されるのでは?」と心配される方もいますが、香典は没収されません。
葬祭扶助はあくまで「最低限の葬儀を行うための費用補助」であり、参列者からいただく香典は遺族に対する弔意の表れとして扱われます。そのため、香典が収入認定されて生活保護費が減額されることはありません。
ただし、注意点もあります。
香典が非常に高額になった場合、生活保護の継続に影響を与える可能性がある
葬祭扶助を利用せずに通常の葬儀を行い、多額の香典収入があると「経済的に葬儀費用を負担できるのでは」と判断されることがある
香典返しなどを準備すると、逆に出費がかさんでしまうケースもある
このように香典は没収されるものではありませんが、取り扱いに注意が必要です。
基本的に、香典は遺族の気持ちを支えるものとして安心して受け取れると覚えておけば大丈夫です。
4.2 香典収入と生活保護の取り扱い
香典は没収されないものの、生活保護を受けている方にとっては「収入」と見なされる可能性があるのか気になるところです。結論から言うと、通常の範囲で受け取る香典は生活保護の収入認定には含まれません。
これは、香典があくまで葬儀に付随して発生する一時的な弔意の表れであり、日常生活のための収入とは性質が異なるためです。そのため、香典を受け取ったからといって生活保護費が減額されることはありません。
ただし、次のような点には注意が必要です。
多額の香典収入があった場合、自治体によっては報告を求められることがある
香典返しを行うと自己負担が大きくなり、結果的に家計を圧迫することがある
香典を故人の供養以外に使った場合、誤解を招くことがある
よくある誤解として、「香典を受け取ると生活保護が打ち切られるのでは」と不安になる方がいますが、その心配はありません。香典は生活支援のための収入ではなく、弔意を表すものであるという点を役所も理解しています。
香典は生活保護制度に影響を与えるものではなく、安心して受け取れるものと覚えておくと安心です。
▶︎5. 生活保護の仏事費用に関するよくある失敗と注意点
5.1 事前申請を忘れて葬儀を行ってしまうケース
葬祭扶助を利用するうえで、もっとも多い失敗のひとつが事前申請を忘れて葬儀を行ってしまうことです。
葬祭扶助は「事前に役所へ申請し、承認を受けること」が条件になっています。そのため、葬儀を先に進めてしまった場合、後から申請しても補助が受けられません。
よくある流れとしては、
身内が急に亡くなり、慌てて葬儀社と契約してしまう
喪主が制度の存在を知らず、そのまま葬儀を済ませてしまう
葬儀後に生活保護を受けていることを思い出し、役所に相談したが手遅れだった
といったケースです。
この失敗を避けるためのポイントは、
亡くなったらすぐに役所の生活保護担当課へ連絡する
契約前に「葬祭扶助を利用したい」と必ず伝える
葬儀社に依頼する際も、葬祭扶助に対応しているか確認する
こうした手順を踏めば、補助を確実に受けられます。
大切なのは、悲しみの中でも一度立ち止まり、役所に相談してから葬儀を進めることです。
5.2 経済力があると判断されて葬祭扶助が却下されるケース
葬祭扶助は、生活保護を受けている方の葬儀費用を支援する制度ですが、申請しても必ず承認されるとは限りません。代表的な理由のひとつが、「経済力がある」と判断されてしまうケースです。
具体的には以下のような状況が対象外となることがあります。
故人に預貯金が残っており、それで葬儀費用をまかなえる場合
喪主や親族に十分な収入・資産があると見なされる場合
扶養義務のある親族が近くに住んでいて、経済的に援助できると判断される場合
こうした場合、役所は「公的扶助を使わなくても葬儀を行える」と判断し、葬祭扶助の申請を却下することがあります。
よくある失敗例は、
故人の口座にわずかな残高があっただけで安心していたら、葬儀費用に充てるよう指示された
遠方に住む親族が「形式上の扶養義務者」として判断され、援助できないのに却下された
親族が「資産がない」と誤解して申告した結果、後から通帳が確認され問題になった
このようなトラブルを避けるためには、
故人や喪主の資産状況を正直に申告する
親族が経済的に援助できない場合は、その事情を具体的に説明する
不明点があれば葬儀社や役所に事前に相談して確認する
葬祭扶助は本当に支援が必要な方のための制度であるため、経済状況を正しく伝えることが大切です。
5.3 戒名や追加の供養費用が予算を超えてしまうケース
葬祭扶助は火葬に必要な最低限の費用を補助する制度です。そのため、僧侶へのお布施や戒名料、供養のための追加費用は対象外となります。ここでよくあるのが、戒名や供養の費用が予算を超えてしまうケースです。
代表的な失敗例は次の通りです。
葬祭扶助でまかなえると思い込み、僧侶へ依頼して後から自己負担が発生した
家族葬を希望して式場を手配したが、補助対象外で予算が大幅に超えた
供養のために副葬品や花祭壇を追加し、結果的に高額になってしまった
こうした問題を防ぐには、葬祭扶助で補助される範囲を明確に理解することが大切です。戒名や法要など宗教的な儀式を希望する場合には、別途費用が必要であることを前提に準備しておく必要があります。
また、最近では一日葬や家族葬といった小規模な形式を選ぶ方も増えています。これにより、従来よりも時間的・金銭的な負担を軽減できることがあります。
費用面の制約がある中でも、故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、自分たちに合った形の供養を選ぶことが大事です。
▶︎6. 迎福寺が提供する仏事とご供養のご案内
6.1 500年以上の歴史を持つ曹洞宗寺院としての役割
迎福寺は、千葉県印西市にある曹洞宗の寺院で、500年以上の歴史を持っています。開山以来、地域の方々に寄り添いながら、仏事やご供養を支えてきました。
曹洞宗は坐禅を中心とする修行を大切にする宗派であり、日常生活の中に仏の教えを生かすことを重んじています。その教えに基づき、迎福寺でも葬儀や法要を通じて故人を偲び、遺族の心を支える場を提供しています。
また、迎福寺には道元禅師の石像があり、訪れる人々を見守っています。単なる葬儀や法要の場ではなく、心を落ち着け、安心して祈れる空間であることも大きな役割です。
現代社会では葬儀の形も多様化していますが、迎福寺は長い歴史と宗派の伝統を踏まえながら、時代に合わせた柔軟な対応を続けています。地域の方々が安心して相談できる存在であることこそ、迎福寺の使命といえます。
6.2 一日葬や家族葬への柔軟な対応
近年、一日葬や家族葬を希望される方が増えています。迎福寺では、ご宗家の事情に合わせて柔軟に対応しています。
一日葬:通夜を省略し、告別式と火葬を1日で執り行う形式
家族葬:親族や親しい方のみで行い、規模を抑えた温かいお別れ
通常の葬儀に比べて時間と費用の負担が少ない
宗派に沿った儀式を守りつつ、ご家族の希望を尊重
副葬品や式次第もご相談に応じて調整可能
限られた条件の中でも、心を込めて故人を偲ぶことができる形をご提案します。
6.3 経済的負担に配慮したご供養の取り組み
迎福寺では、ご宗家の金銭的・時間的な負担を抑えたご供養を大切にしています。生活保護の葬祭扶助に対応しつつ、無理のない形で故人をお見送りできるよう支援しています。
葬祭扶助を利用しながらのご供養に対応
ご希望に応じた一日葬・家族葬の提案
副葬品の持ち込みや選択も柔軟に対応
不要な追加費用を抑え、安心できるプランをご案内
経済的な事情を考慮した無理のない供養
費用を抑えながらも、心のこもった供養ができることを最も大切にしています。
6.4 法要依頼・お問い合わせのご案内
迎福寺では、葬儀・法要に関するご依頼やご相談を随時受け付けています。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えております。
葬儀や法要の流れを丁寧にご説明
一日葬・家族葬を含むさまざまな形式に対応
副葬品や供養内容のご相談も柔軟に調整可能
年中無休で朝8:30〜19:00まで対応
お問い合わせは電話・Webフォームから可能
大切なご供養の場を安心して迎えていただけるよう、迎福寺がしっかりとサポートいたします。
▶︎7.まとめ
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭扶助制度によって葬儀費用の一部が補助されます。当山付近の地域では20万円前後が一般的な支給額で、火葬を中心とした直葬に必要な費用をまかなうことが可能です。
一方で、僧侶のお布施や戒名料、通夜や告別式の費用は補助対象外となります。そのため、補助の範囲を正しく理解し、事前に役所へ相談・申請することが大切です。また、社会保険からの埋葬料や自治体の市民葬など、追加で利用できる制度を知っておくとさらに安心です。
迎福寺では、一日葬や家族葬への柔軟な対応を行い、ご宗家の時間的・金銭的な負担を抑えながら心を込めたご供養をご提案しています。
制度を正しく理解し、自分たちに合った形のご供養を選ぶことが、安心して故人を見送るための第一歩です。
▶︎お葬式なら迎福寺にお任せください
迎福寺では、心温まる葬儀サービスを提供し、ご遺族の大切な時間をサポートいたします。
葬儀から法要、供養まで、故人と遺族に寄り添うお手伝いをさせていただきます。
葬儀のプランや費用についてのお悩み、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
安心できる葬儀を迎福寺で。
詳細はここからご確認ください。

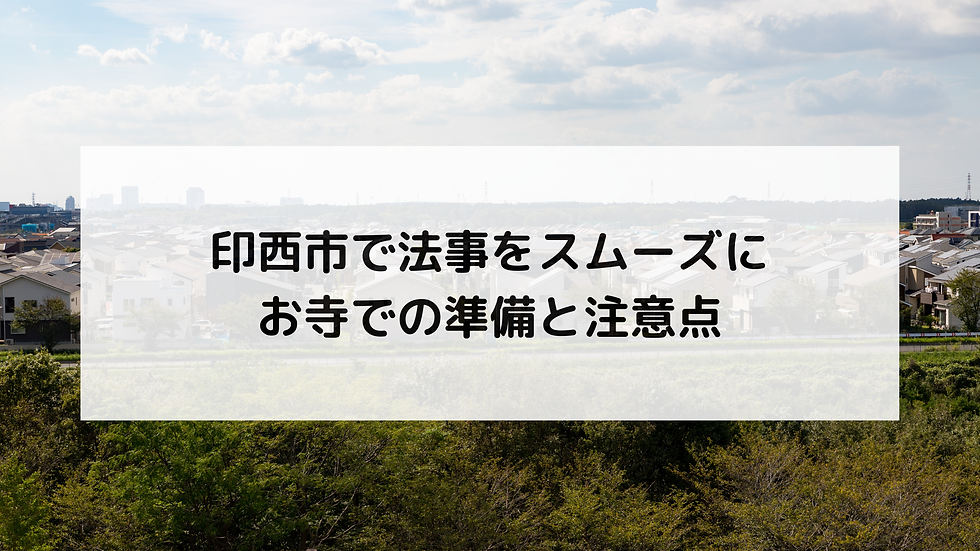

コメント