法事の回忌計算とは?数え方の基本と具体例を解説
- 宗教法人迎福寺
- 2025年1月23日
- 読了時間: 15分

▶︎1. 法事と回忌の基本知識

1.1 法事とは何か
「法事」とは、故人の供養を目的とした仏教の儀式です。僧侶が読経を行い、遺族や親族が集まって故人を偲びます。仏壇の前やお墓で行われることが多く、供養の場として故人との絆を深める大切な時間でもあります。
法事の目的は、故人が極楽浄土へ導かれるように願う「供養」です。遺族にとっても、故人の死を受け入れ、心の整理をする機会となります。法事には、日数や年数ごとに定期的に行う「回忌法要」が含まれます。
1.2 回忌の意味と重要性
「回忌」とは、故人の命日を基準に行う年忌法要のことです。一周忌は亡くなってから1年後、三回忌は2年後に行われるように、回忌法要は命日を迎えるたびに故人を供養する儀式を指します。
仏教の教えでは、故人が成仏するためには、一定期間の供養が大切とされています。特に三回忌までは、故人の魂が浄化される重要な期間と考えられているため、多くの遺族が丁寧に回忌法要を行います。
■ 回忌法要の目的
故人の成仏を願う
仏教では、亡くなった方が迷いの世界に行かないよう、供養が必要とされています。読経や供え物を通じて、故人が安らかに成仏することを願います。
遺族の心の整理
回忌法要を行うことで、遺族は改めて故人の存在を思い出し、心の中で故人との別れを受け入れていきます。
1.3 法事と回忌の違い
「法事」と「回忌」はどちらも故人を供養する行事ですが、内容に違いがあります。簡単に言うと、法事は故人の供養全般を指し、回忌はその中でも特に命日に行う年忌法要を指します。
■ 法事の特徴
忌日法要(初七日、四十九日)や回忌法要など、故人のための供養儀式全般を含みます。
故人の冥福を祈り、遺族が集まることで家族の絆を深める場にもなります。
■ 回忌の特徴
一周忌、三回忌、七回忌など、命日を基準に行われる法要です。
命日ごとに行う法要のスケジュールが決まっているため、正確な回忌計算が大切になります。
どちらも故人を偲ぶ大切な供養ですが、回忌法要は特に故人の命日を意識した供養です。「法事」という大きな枠組みの中に、回忌という年忌法要が含まれていると考えると分かりやすいですよ。
▶︎2. 回忌計算の方法と具体例

2.1 回忌の数え方の基本ルール
回忌の数え方は、命日を1回目(初回)とし、翌年から年数を重ねていく方法です。たとえば、亡くなった日を基準として「一周忌」は亡くなった翌年の同じ日に行います。その後は、「三回忌」「七回忌」といった具合に奇数年で回忌法要を行うのが一般的です。
■ 基本の数え方
一周忌:亡くなった翌年の同じ日
三回忌:亡くなってから2年後
七回忌:亡くなってから6年後
十三回忌:亡くなってから12年後
注意!
回忌の「〇回忌」という言葉は、亡くなった年を1回目とカウントする「数え年」の考え方が基になっています。たとえば、三回忌は「3年目」ではなく、亡くなってから2年後に行うのが正しい数え方です。
2.2 具体的な計算例と間違いやすいポイント
回忌計算は一見シンプルですが、数え方を間違えやすいポイントがいくつかあります。特に、命日が年の初めや終わりの場合、間違えないように注意が必要です。
■ 具体的な計算例
2023年3月15日に亡くなった場合の回忌計算 → 一周忌:2024年3月15日 → 三回忌:2025年3月15日
2023年12月10日に亡くなった場合の回忌計算 → 一周忌:2024年12月10日 → 三回忌:2025年12月10日
■ 間違いやすいポイント
命日の年を数え忘れる
亡くなった年が「1回目」となるため、これを忘れると数え方がズレてしまいます。
法要のタイミングがずれる
回忌法要は命日の前後に行うことが一般的ですが、「翌年の同じ日」と意識することが重要です。
2.3 計算ミスを防ぐための注意点
回忌計算は正確さが大切です。法要を間違った日に行ってしまうと、故人の供養として十分ではないと考えられることもあります。計算ミスを防ぐためには、次のポイントを押さえましょう。
■ 計算ミスを防ぐポイント
命日をカレンダーに記録する
命日をカレンダーに記入しておくと、回忌のタイミングを間違えずに把握できます。
家族で共有する
回忌法要は家族全員で行うものです。命日を家族で共有し、スケジュールを確認しておくと安心です。
お寺に相談する
計算に不安がある場合は、お寺の住職に相談すると間違いを防げます。プロに確認してもらうことで、確実な日程で法要を行えますよ。
▶︎3. 法事の種類と時期の目安

3.1 忌日法要と年忌法要の違い
法事には大きく分けて「忌日法要」と「年忌法要」があります。どちらも故人の供養を目的とした儀式ですが、行う時期や目的が異なるので、しっかり区別しておきましょう。
■ 忌日法要とは?
忌日法要は、故人が亡くなった日から四十九日までの期間に行われる法要のことです。この期間を「忌中」と呼び、亡くなった方が成仏するまでの重要な期間と考えられています。
主な忌日法要のタイミングは以下の通りです。
初七日(しょなのか):亡くなってから7日目
四十九日:亡くなってから49日目
百箇日(ひゃっかにち):亡くなってから100日目
四十九日法要は特に重要で、この日をもって忌明けとされるため、家族や親族が集まり、盛大に供養するのが一般的です。
■ 年忌法要とは?
年忌法要は、故人の命日を基準に、1年後、2年後、6年後…といった節目の年に行われる法要です。これを「回忌法要」とも呼び、亡くなった年を1回目として、二周忌、三回忌、七回忌などを行います。
三回忌までは重要な法要とされるため、多くの遺族が丁寧に行いますが、十三回忌以降は省略する場合もあります。
3.2 各法要のタイミングと目的
法事の種類ごとに、行う時期と目的をしっかり押さえておきましょう。
■ 忌日法要の目的
初七日~四十九日:故人が無事に成仏するよう祈る
百箇日:遺族が悲しみから立ち直り、生活を整える区切り
四十九日を過ぎると「忌明け」となり、故人が成仏したと考えられます。この日には墓石を建てたり、納骨式を行ったりすることも多いです。
■ 年忌法要の目的
一周忌:故人が亡くなってから1年後の命日に行い、改めて供養を行う
三回忌:亡くなってから2年後に行い、故人を偲ぶ大切な法要
七回忌以降:故人を家族の記憶に留め、命日ごとに供養する
年忌法要の回数が増えるごとに、法要の規模は小さくなることが一般的です。
3.3 宗派や地域による違い
法事の内容やタイミングは、宗派や地域の風習によって異なる場合があります。
■ 宗派による違い
浄土宗・浄土真宗:四十九日までの忌日法要を特に重視
曹洞宗・臨済宗:一周忌、三回忌、七回忌を重要な節目として行う
日蓮宗:法華経に基づく独自の読経スタイルがある
宗派によって、法要で読むお経や儀式の順序も異なるため、お寺の住職に確認するのが安心です。
■ 地域による違い
地域の風習によっても、法要の行い方が変わります。
都市部:簡略化された法要が増えている
地方:伝統的な風習を守り、大規模な法要を行うことが多い
たとえば、地方によっては「初盆」(新盆)を盛大に行い、親族や知人が集まる大きな行事になることもあります。
▶︎4. 法事の準備とマナー
法事をスムーズに進めるためには、事前の準備がとても大切です。特に遺族が主催する場合、招待状の作成や当日の流れの把握、そして服装やお布施のマナーなど、事前に確認しておくべきポイントが多くあります。ここでは、法事の準備から当日の流れまでを詳しく解説します。
4.1 法事の準備手順
法事を行う際は、開催の3〜4週間前には準備を始めるのが一般的です。法事には親族や親しい知人を招待することが多いため、早めの段取りが重要ですよ。
■ 法事準備のステップ
日程と場所の決定
僧侶の都合も確認しながら、命日や回忌法要のタイミングに合わせて日程を決めます。法要は自宅や墓地、お寺で行われることが一般的です。
僧侶への依頼
法事を行う際は、菩提寺の住職に読経をお願いします。お寺によっては、読経料として「お布施」を用意する必要があります。
招待者リストの作成
親族や親しい知人に案内を送るため、招待者リストを作成します。故人との関係を考慮し、招待すべき人を選びましょう。
会食の手配
法事後に会食を行う場合、仕出し料理を手配するか、法要会場近くの会食場所を予約します。参加人数を把握して、無駄のない手配を心がけましょう。
お供え物や供花の準備
故人の好物をお供え物として用意したり、供花を手配します。法事の際には、故人を偲ぶ意味で季節の花などを飾るのが一般的です。
4.2 招待状の作成とお供え物の選び方
法事の招待状を送る際は、故人の名前、日時、場所、主催者名を記載し、法事の趣旨が伝わるようにします。
■ 招待状の基本構成
件名:「○○法要のご案内」
本文:「故○○の○回忌法要を執り行いますので、ご案内申し上げます。」
日時:○○年○月○日(○曜日)○時~
場所:○○寺 ○○市○○町○○
■ お供え物の選び方
法事のお供え物は、故人の好きだったものを選ぶのが一般的です。ただし、地域や宗派の習慣によって異なる場合もあるため、確認しておきましょう。
果物:リンゴ、バナナ、ブドウなど
お菓子:和菓子、羊羹など
飲み物:故人が生前好きだった飲み物(お酒など)
注意!
香りの強いものや傷みやすい食品は避けましょう。
4.3 当日の流れと服装・お布施のマナー
法事当日は、読経から会食までの一連の流れを把握しておくとスムーズに進められます。
■ 当日の流れ
僧侶の読経 法事の開始時間までに僧侶が到着し、読経を行います。
焼香 僧侶の読経中に、遺族や参列者が順番に焼香を行います。
法話 僧侶による法話が行われる場合もあります。
会食 法事の後は、親族での会食を行うことが一般的です。
■ 服装のマナー
法事の服装は、喪服か黒の礼服が基本です。男性はブラックスーツ、女性は黒のワンピースやスーツを選び、アクセサリーは控えめにしましょう。
■ お布施のマナー
お布施は白い封筒に入れ、表書きに「御布施」と記載します。金額の相場は、1万〜5万円程度が一般的ですが、地域やお寺によって異なるため事前に確認しましょう。
▶︎5. よくある質問と注意点
法事を行う際、慣れていないと「これで合っているのかな?」と不安に感じることが多いですよね。ここでは、法事に関するよくある質問とその解決策、お布施の相場と渡し方、そしてお寺への相談方法について詳しく解説します。
5.1 法事での疑問とその解決策
法事を準備する際には、さまざまな疑問が出てきます。特に、「何をいつまでに準備すればいいの?」といったタイミングの不安が多いですよね。ここでは、よくある疑問をいくつか取り上げ、その解決策をお伝えします。
■ Q1. 法事はいつまでに準備を始めるべき?
A. 法事は遅くとも3〜4週間前には準備を始めましょう。僧侶のスケジュール確認や会食の手配、招待状の送付など、事前にやるべきことが多いからです。早めに準備を進めることで、余裕を持って当日を迎えられますよ。
■ Q2. 法事にどこまでの親族を招待するべき?
A. 親族の範囲は法事の規模によって異なります。一周忌や三回忌などの大切な法要では、故人の直系親族や親しい親族を招待するのが一般的です。ただし、地域の風習や家族の考えによって異なるため、事前に相談しましょう。
■ Q3. 法事で何をお供えするのが良い?
A. 故人の好きだったものを用意するのが良いとされています。一般的には果物や和菓子、故人が好きだった飲み物などを選ぶのが無難です。ただし、お供え物には地域や宗派による違いもあるため、お寺に相談すると安心です。
5.2 お布施の相場と渡し方
お布施は、法事の際に僧侶へ渡す感謝の気持ちを表すものです。金額の相場や渡し方に悩む方も多いですが、ここでは基本的なマナーについて説明します。
■ お布施の相場
一周忌・三回忌:1万~5万円が一般的
四十九日法要:3万~5万円
それ以降の年忌法要:1万~3万円
ただし、金額はお寺の規模や地域の習慣によって異なります。お寺に確認するのが確実ですよ。
■ お布施の渡し方
白い封筒に入れる 封筒の表書きには「御布施」と書き、黒墨を使用します。
袱紗(ふくさ)に包む お布施を渡す際は、封筒を袱紗に包んで持参します。
法事が始まる前に渡す 法事が始まる前に、お寺の住職に「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えて渡すのがマナーです。
5.3 お寺への相談方法
法事に関する疑問がある場合は、お寺の住職に直接相談するのが一番安心です。特に、回忌の計算や法要の進め方についてはプロの意見を聞くことで、間違いを防げますよ。
■ お寺に相談するときのポイント
早めに連絡する
住職も多くの法事を抱えているため、早めに相談してスケジュールを確認しましょう。
具体的な内容を伝える
法事の種類、命日、招待者の人数など、具体的な内容を伝えることで、的確なアドバイスをもらえます。
遠慮しない
法事は慣れていない人が多いため、住職も親切に教えてくれます。「これを聞いてもいいのかな?」と遠慮せず、分からないことはしっかり聞きましょう。
▶︎6. 迎福寺での法事サポート
千葉県印西市にある曹洞宗の寺院「迎福寺」では、法事のサポートを丁寧に行っています。迎福寺では、初七日から回忌法要まで幅広い法事の依頼を受け付けており、地域に根ざした安心感のあるお寺として親しまれています。ここでは、迎福寺が提供する法事サポートの内容や利用方法について詳しく説明します。
6.1 迎福寺が提供する法事サポート
迎福寺では、故人の供養を丁寧にサポートしています。法要の内容はもちろん、準備や進行の相談にも対応してくれるので、法事が初めての方でも安心して依頼できます。
■ 主な法事サポート内容
忌日法要・年忌法要の実施
初七日、四十九日、一周忌、三回忌など、各種法要を執り行います。命日を基準に、正しいタイミングで供養を行えるようアドバイスしてくれます。
読経の依頼と進行サポート
住職が読経を担当し、焼香や法話などの法事の流れを丁寧にサポートしてくれます。
納骨や墓参りの手配
法要に合わせて納骨や墓参りのサポートも可能です。お墓の準備が整っていない場合も相談に乗ってくれます。
6.2 施設の特徴と利用方法
迎福寺の施設は、法事を行うのにふさわしい静かな環境が整っています。落ち着いた雰囲気の本堂で、家族が心を込めて故人を偲ぶことができます。
■ 迎福寺の施設の特徴
本堂:広々とした本堂で、読経や焼香などの法要を行えます。
控室:法事前後に親族が利用できる控室も完備されています。
駐車場:車で来られる方のために、広い駐車場が用意されています。
■ 利用方法
法事の希望日を決める
命日を基準に、希望する法要の日時を迎福寺に連絡します。
法要内容の相談
法事の種類、招待者数、お供え物など、具体的な内容を住職と相談します。
当日に向けた準備
法事当日は、迎福寺の案内に従って進行します。親族がリラックスして法要に臨めるよう、事前の準備をサポートしてくれます。
6.3 予約から法要当日までの流れ
迎福寺で法事を行う際の予約から当日までの流れを、具体的に説明します。
■ 法事の流れ
電話またはメールで予約
まずは、迎福寺に連絡して法事の日時を相談します。 この際、命日や回忌のタイミングについても確認できます。
事前打ち合わせ
法事の種類、招待者数、お布施の準備など、必要な項目を住職と打ち合わせします。
法事当日
法事当日は、住職の案内に従いながら進行します。読経、焼香、法話が終わったら、墓参りや会食へと進むことも可能です。
迎福寺では、法事の準備から当日の進行まで、丁寧にサポートしてくれます。
▶︎7. まとめ
ここまで、法事の意味や回忌計算の方法、準備と進め方について詳しく説明してきました。法事は故人を偲び、家族の絆を深める大切な儀式です。正しいタイミングで行うことで、より安心して供養を行えます。それでは、重要なポイントをもう一度振り返りましょう。
7.1 法事と回忌計算の重要性
法事は、故人の成仏を願う大切な儀式です。特に、回忌法要は命日を基準に正確に行うことが重要です。仏教の教えでは、故人が迷いなく極楽浄土へ導かれるためには、定期的な供養が必要とされています。法事は単なる形式ではなく、家族が故人のことを思い出し、心を込めて祈る機会でもあります。
正確な回忌計算を行うことで、供養のタイミングを逃さず、故人の魂が安らかに浄化されることを願うことができます。
7.2 正確な回忌計算で安心した法事を
回忌計算は、命日から数える「数え年」の考え方に基づきます。この数え方を間違えると、法事のタイミングがずれてしまうことがあるので注意が必要です。
■ 正確な回忌計算のポイント
亡くなった年を1回目とカウントする
命日を基準に、翌年以降の法要を計算する
間違いが心配な場合は、お寺に相談する
法事の準備をする際は、家族間でしっかりと日程を共有し、法事当日に向けて早めに準備を進めることが大切です。
正しい回忌計算を行うことで、遺族も安心して法事に臨めます。
7.3 迎福寺のサポートを活用しよう
迎福寺は、法事の準備から当日の進行まで丁寧にサポートしてくれます。初めて法事を主催する方でも、迎福寺に相談すれば安心して回忌法要を行えますよ。
迎福寺では、次のようなサポートを提供しています。
忌日法要・年忌法要の実施
読経の依頼と進行サポート
納骨や墓参りの手配
法事に不安がある方も、迎福寺の住職に相談することで、スムーズに準備を進めることができます。
迎福寺のような頼りになるお寺を活用すれば、故人の供養を心を込めて行うことができ、家族の絆をより一層深める時間を持つことができるでしょう。
▶︎千葉県印西市の法事や法要なら宗教法人迎福寺へ
法事や法要は、故人を供養する大切な儀式です。宗派や地域によっても進行が異なるため、しっかりとした知識が必要です。宗教法人迎福寺では、あなたの大切な法事を心を込めてサポートいたします。お手伝いが必要な方は、ぜひご相談ください。

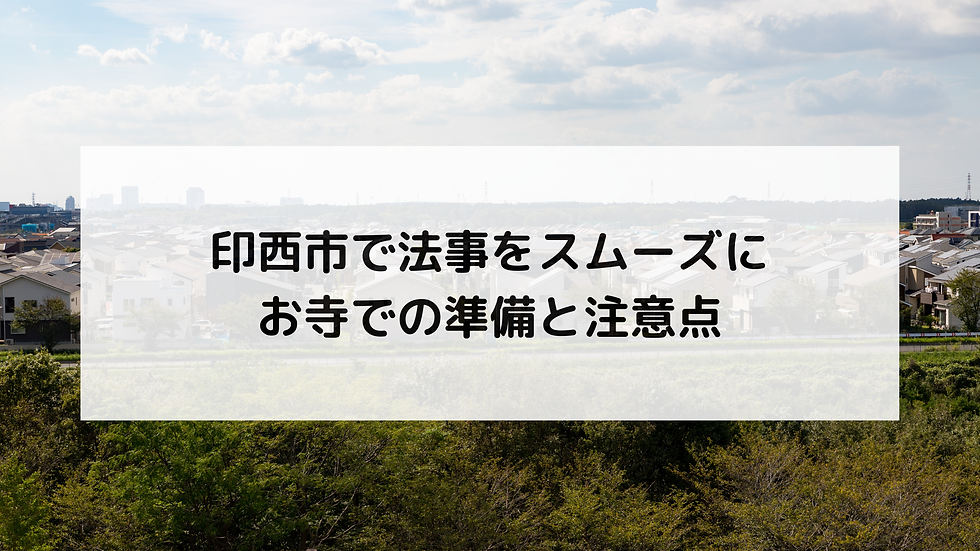

コメント