失礼のない法事の作法|正しい服装・お布施・会食マナーをチェック!
- 宗教法人迎福寺
- 2025年2月24日
- 読了時間: 17分

▶︎1. 法事の作法とは?基本を知ろう

1.1 法事とは?意味と目的
法事とは、故人を偲び、供養するための仏教の儀式です。
亡くなった方への感謝や冥福を祈るために行われるもので、仏教の教えに基づいた大切な行事です。法事は、故人の魂が安らかに成仏することを願い、遺族や親族が集まってお経をあげたり、供物を捧げたりします。
法事の目的とは?
法事を行う目的には、次のようなものがあります。
故人の供養:亡くなった方の魂を慰め、極楽浄土へ導くため
遺族や親族の絆を深める:家族や親族が集まり、思い出を共有する機会
仏教の教えを実践する:感謝や思いやりの心を持つため
法事はなぜ行うの?
仏教では、人は亡くなった後、一定の期間を経て次の世界へ旅立つと考えられています。その間、遺族が読経やお供えをすることで、故人の魂が迷わず安らかに過ごせるようになるとされています。また、法事を通じて、残された人々が故人の教えや生き方を振り返り、自身の生き方を見つめ直す機会にもなります。
1.2 法事の種類とタイミング
法事にはさまざまな種類があり、それぞれ行う時期が決まっています。大きく分けると、亡くなってすぐに行われる「忌明け法要」と、毎年・数年ごとに行う「年忌法要」に分かれます。
忌明けまでの法事
亡くなった直後から四十九日までは、故人の魂が成仏できるように供養する期間とされています。
初七日(しょなのか):亡くなった日を含めて7日目に行う法要。故人が無事に旅立てるように祈ります。
四十九日(しじゅうくにち):亡くなって49日目に行う重要な法要。忌明けとされ、お墓への納骨を行うことも多いです。
百か日(ひゃっかにち):亡くなって100日目に行われる法事で、遺族が悲しみを乗り越える節目とされています。
年忌法要(祥月命日)
忌明け以降は、故人の冥福を祈るために年忌法要を行います。
一周忌(いっしゅうき):亡くなって1年後に行う法要で、初めての年忌法要です。親族が集まり、改めて故人を偲びます。
三回忌(さんかいき):亡くなって2年後(満2年)に行う法事。一周忌と並んで大切な節目とされます。
七回忌(しちかいき)以降:亡くなって6年目(満6年)に行い、その後は13回忌、17回忌、33回忌と続いていきます。
法事の日程の決め方
法事は、故人の命日を基準に日取りを決めます。ただし、命日が平日で都合がつかない場合は、直前の土日などに変更することも一般的です。また、年忌法要の中でも、三回忌以降は親族の状況を考慮して省略するケースもあります。
1.3 法事と法要の違い
「法事」と「法要」は似た言葉ですが、意味が少し異なります。
法要とは?
法要とは、僧侶がお経をあげ、故人を供養する仏教儀式のことを指します。一般的に、四十九日法要や年忌法要などがこれにあたります。僧侶の読経のほかに、お焼香や供物の準備を行い、仏教の教えに沿った形で故人を偲びます。
法事とは?
一方で法事は、法要に加えて、その後の会食や親族の集まりなどを含めた行事全体のことを指します。法要を執り行った後、会食をしながら故人の思い出を語り合うことが多く、遺族や親族の絆を深める大切な時間となります。
法事と法要の違いまとめ
法要:僧侶による読経や供養の儀式そのもの
法事:法要に加えて、その後の会食や親族の集まりを含む行事全体
例えば、一周忌の際にお寺でお経をあげてもらうのが「法要」、その後に親族で集まり食事をするところまで含めると「法事」となります。どちらも故人を偲ぶ大切な時間であり、仏教の教えを守りながら行うことで、心を込めた供養となるのです。
▶︎2. 法事の準備と進め方

2.1 法事の案内状の作法とマナー
法事の案内状は、招待する方への気遣いを込めて送る大切なものです。適切なタイミングで、失礼のない文面を用意することがポイントです。
法事の案内状を送る時期
法事の案内状は、法要の1か月前から2週間前までに送るのが一般的です。特に遠方の方がいる場合は、早めにお知らせすると親切です。
案内状に記載すべき内容
案内状には、以下の項目をわかりやすく記載します。
故人の名前と法事の種類(例:一周忌法要、三回忌法要など)
日時と場所(会場の住所、集合時間などを明記)
会食の有無(会食がある場合はその旨を伝える)
服装の指定(喪服や平服の指定がある場合は明記)
返信のお願い(出欠の確認が必要な場合は返信期限を記載)
口頭やメールでの案内も可能
最近では、親しい親族や少人数での法事の場合、口頭やメールでの案内も増えています。ただし、年配の方には従来の書面での案内を送る方が丁寧な印象を与えるため、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。
2.2 会場の準備と供物の手配
法事の会場準備は、故人を偲び、参列者をお迎えするための大切な工程です。また、供物の手配も、故人への供養として欠かせません。
法事の会場選びと準備のポイント
法事の会場は、お寺・自宅・会館(斎場)・墓前のいずれかで行うのが一般的です。
お寺で行う場合:本堂で僧侶による法要を執り行い、その後、会食を行うことが多いです。
自宅で行う場合:仏壇の前に祭壇を用意し、僧侶を招いて読経を行います。
会館や斎場を利用する場合:設備が整っているため、準備の負担が少なく、駐車場の心配も不要です。
墓前で行う場合:屋外のため、天候に配慮し、事前にお墓の掃除をしておきます。
いずれの会場でも、仏壇や祭壇を清め、供物や花を整えることが重要です。
供物の準備と選び方
供物とは、故人の霊を慰めるためにお供えする品のことです。地域や宗派によって異なりますが、一般的には以下のようなものが選ばれます。
果物:りんご・みかん・梨など、季節の果物が好まれます。
お菓子:和菓子(羊羹・饅頭など)が定番ですが、故人が好んだお菓子を供えることもあります。
お花:菊・ユリ・カーネーションなど、白を基調とした供花が一般的です。
お線香・ローソク:法事用のお線香やローソクも準備しておきます。
故人の好物:特に決まりはなく、故人が生前好きだった食べ物や飲み物を供えても問題ありません。
供物の並べ方とマナー
供物は、仏壇や祭壇の中央に供えるのが基本です。
果物やお菓子は、箱やかごに入れたままではなく、お皿に盛り付ける
仏壇の前に配置する場合、手前には線香・ローソク、奥に果物やお菓子を置く
「四つ足生臭もの(肉・魚)」は避ける(精進料理の考えに基づく)
供物は、法要後に参列者で分け合うことが多いため、個包装されたお菓子や持ち帰りやすい果物を選ぶと喜ばれます。
2.3 僧侶への依頼とお布施の準備
法事を執り行う際には、僧侶に読経をお願いするのが一般的です。僧侶への依頼の仕方やお布施の準備には、いくつかのマナーがあるので、事前に確認しておきましょう。
僧侶への依頼方法
僧侶への依頼は、法事の日程が決まり次第、なるべく早めに行うのが理想です。
菩提寺(先祖代々のお寺)がある場合:直接お寺に連絡し、住職の予定を確認する。
菩提寺がない場合:インターネットや葬儀社の紹介サービスを利用して、僧侶を手配する。
依頼時には、法要の日時・会場・参列者の人数・会食の有無などを伝えましょう。特に、宗派によって法事の作法が異なるため、宗派を確認しておくことが重要です。
お布施とは?
お布施とは、読経をしていただいた僧侶への謝礼です。金額に決まりはありませんが、法要の規模や地域によって相場が異なります。
お布施の金額の目安
お布施の金額は、一般的に以下のような目安があります。
四十九日・一周忌法要:3万円~5万円程度
三回忌以降の法要:1万円~3万円程度
お車代(僧侶が遠方から来る場合):5,000円~1万円程度
御膳料(会食に参加されない場合):5,000円~1万円程度
お布施の金額は、お寺や地域によって違うため、事前に確認しておくと安心です。
お布施の包み方と渡し方
お布施は、白無地の封筒または奉書紙(ほうしょがみ)に包みます。表書きには、「御布施」と記入し、裏面に施主(法事を主催する人)の氏名を記載します。
渡す際のマナーも大切で、次の点に注意しましょう。
ふくさ(袱紗)に包んで持参し、渡す際にふくさを開く
法要が始まる前に、控室などで僧侶に手渡す
「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えて渡す
僧侶によっては、直接お布施を受け取らない場合もあるので、お寺の方針に従いましょう。
▶︎3. 法事当日の作法と注意点

3.1 服装のマナー(喪服・平服の選び方)
法事の際の服装は、故人を偲び、失礼のないように選ぶことが大切です。服装の格式や選び方には、いくつかのポイントがあるので、事前に確認しておきましょう。
法事の服装の基本ルール
法事の服装は、法要の規模や回忌によって異なります。基本的には、一周忌までは喪服、それ以降の法事では平服(略喪服)でも可とされています。
男性の服装
一周忌まで:ブラックスーツ、白シャツ、黒ネクタイ、黒い革靴
三回忌以降:ダークスーツ(黒・濃紺・グレー)、地味なネクタイ(黒・グレー)、黒い革靴
注意点:派手なネクタイや光沢のあるスーツは避ける
女性の服装
一周忌まで:黒のワンピースやアンサンブル、黒いストッキング、黒のパンプス
三回忌以降:地味な色(黒・紺・グレー)のワンピースやスーツでもOK
注意点:肌の露出を避け、アクセサリーは真珠など控えめなものにする
子どもの服装
男の子:白シャツ+黒や紺のズボン
女の子:黒や紺のワンピース、白のブラウス+黒スカート
注意点:派手なデザインやキャラクターものは避ける
靴・バッグ・小物のマナー
靴:黒のシンプルなデザインが基本(光沢のある素材や派手なデザインはNG)
バッグ:黒の布製や革製でシンプルなデザインのもの
アクセサリー:結婚指輪以外は控えめに(真珠のネックレスは可)
ネイル・髪型:派手なネイルは避け、髪は落ち着いた色にまとめる
夏や冬の服装の注意点
夏場:半袖OKだが、ノースリーブは避ける。日傘や羽織ものを活用する
冬場:黒や紺のコートを着用(ファーや光沢のある素材は避ける)
服装の選び方で迷った場合は、「控えめで上品」を意識すると失礼がありません。
3.2 お焼香の正しい作法
お焼香は、故人の冥福を祈る大切な儀式です。しかし、宗派によって作法が異なるため、正しい方法を知っておくことが大切です。
お焼香の意味とは?
お焼香には、故人の冥福を祈るとともに、自分自身の心身を清める意味があります。香の煙によって場を清め、仏様や故人に敬意を表する行為とされています。
お焼香の種類
お焼香には、大きく分けて3つの方法があります。
立礼焼香(りつれいしょうこう):立ったまま行う方法(一般的な葬儀や法事で用いられる)
座礼焼香(ざれいしょうこう):座った状態で行う方法(自宅や寺院の座敷での法要で用いられる)
回し焼香(まわししょうこう):参列者が順番に香炉を回して行う方法(小規模な法事で用いられる)
一般的なお焼香の流れ
お焼香の基本的な作法は、以下の手順で行います。
祭壇の前で一礼する(または遺族に軽く会釈)
焼香台の前に進み、遺影に向かって合掌する
香をつまみ、香炉にくべる(回数は宗派によって異なる)
再び合掌し、故人の冥福を祈る
一歩下がり、遺族に軽く会釈してから席に戻る
宗派によるお焼香の違い
宗派によって、お焼香の回数や作法が異なります。
浄土宗:1回
浄土真宗(本願寺派):香を額に押し頂かずに1回
浄土真宗(大谷派):2回(香を額に押し頂かない)
曹洞宗:2~3回
臨済宗:1回(香を額に押し頂く)
日蓮宗:1~3回(香を額に押し頂く)
どの宗派でも、作法を間違えてしまっても心を込めて供養することが大切です。わからない場合は、僧侶や他の参列者のやり方を見て合わせるとよいでしょう。
お焼香の際のマナー
数珠を持参し、合掌の際に使用する
大きな音を立てないように静かに焼香する
順番待ちの際は、前の人との間隔を適度にあける
強い香水や派手な服装は控える
お焼香は、形式よりも故人を偲ぶ気持ちが大切です。丁寧な所作で、心を込めてお焼香を行いましょう。
3.3 法事での挨拶の仕方
法事では、施主(主催者)が参列者に向けて挨拶をする場面があります。適切な言葉を選び、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
法事の挨拶をするタイミング
法事で挨拶をするタイミングは、主に以下の3つです。
開式の挨拶(法要が始まる前)
法要後の挨拶(読経が終わった後)
会食時の挨拶(食事が始まる前や終了後)
それぞれの場面に合わせた挨拶の例文をご紹介します。
1. 開式の挨拶(法要が始まる前)
法事が始まる前に、参列者への感謝を伝え、法要を執り行うことを伝えます。
例文:「本日は、ご多忙の中、亡き○○(故人の名前)の一周忌(または三回忌など)にお集まりいただき、誠にありがとうございます。これより、○○の冥福を祈り、法要を執り行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。」
2. 法要後の挨拶(読経が終わった後)
読経が終わった後は、僧侶と参列者への感謝を述べます。
例文:「皆さま、本日はお忙しい中、○○(故人の名前)のためにお集まりいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、無事に法要を終えることができました。また、ご住職(僧侶の方)にはお経をあげていただき、心より感謝申し上げます。」
3. 会食時の挨拶(食事が始まる前)
会食の席では、改めて感謝を伝え、和やかな雰囲気を作ります。
例文:「本日は○○の一周忌にお集まりいただき、ありがとうございました。皆さまとともに故人を偲び、思い出を語り合うことができればと思います。ささやかではございますが、お食事を用意いたしましたので、ごゆっくりお召し上がりください。」
挨拶のポイント
長すぎず、簡潔にまとめる
参列者と僧侶への感謝の気持ちを伝える
故人を偲ぶ言葉を添える
法事での挨拶は、形式よりも心を込めて伝えることが大切です。自然な言葉で、感謝の気持ちをしっかり表しましょう。
▶︎4. 法事後の対応とお礼のマナー
4.1 会食の作法と食事の注意点
法事後の会食は、故人を偲びながら参列者と共に過ごす大切な時間です。食事を通じて故人の思い出を語り合い、親族や参列者とのつながりを深める場となります。
法事の会食の意味
法事後の食事には、次のような意味があります。
故人を偲ぶ時間を共有する
参列者への感謝の気持ちを表す
故人の好きだった食事を楽しみ、供養する
会食は形式的なものではなく、和やかな雰囲気の中で思い出話をすることが大切です。
会食のマナーと流れ
施主(主催者)が最初に挨拶をする
「本日は○○の法要にご参列いただき、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、お食事をご用意いたしましたので、ごゆっくりお過ごしください。」
僧侶がいる場合は、僧侶を優先して席に案内する
食事が始まる前に、故人に手を合わせる
静かで落ち着いた雰囲気の中で食事を楽しむ
法事の食事での注意点
精進料理が基本
仏教の考え方に基づき、肉や魚を避けた精進料理が供されることが多いですが、近年では普通の和食を提供する場合もあります。
箸のマナーに注意する
箸渡し(箸から箸へ食べ物を渡す行為)は、骨上げの作法を連想させるため避ける。
お酒の飲みすぎに注意
法事の席ではお酒が提供されることもありますが、故人を偲ぶ場なので節度を守ることが大切です。
会食後の締めの挨拶
食事が終わった後は、施主が締めの挨拶を行います。
例文:「本日は○○の法要にお越しいただき、ありがとうございました。皆さまとともに故人を偲ぶことができ、感謝申し上げます。これからも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」
法事の会食は、故人を偲びながら和やかに過ごすことが大切です。落ち着いた雰囲気の中で、感謝の気持ちを忘れずにおもてなししましょう。
4.2 お布施・御香典のお礼と返礼品の渡し方
法事では、お布施や御香典をいただいた方へ感謝の気持ちを伝えることが大切です。適切なマナーを守り、失礼のないようにお礼をしましょう。
お布施のお礼の仕方
法要の読経をしてくださった僧侶には、「お布施」として謝礼をお渡しします。
お布施の金額の目安
一周忌・三回忌などの法要:3万円〜5万円
それ以降の法要:1万円〜3万円
お車代(僧侶が遠方から来る場合):5,000円〜1万円
御膳料(会食に参加されない場合):5,000円〜1万円
お布施の渡し方
白無地の封筒や奉書紙に包む(表書きは「御布施」)
ふくさに包んで持参する
法要の前に、施主が僧侶に直接渡す
「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えて渡す
お布施を渡す際は、僧侶の前で直接封筒を開けるのは失礼にあたるため、注意しましょう。
御香典のお礼と返礼品のマナー
法事では、参列者から御香典をいただくことがあります。これに対して、香典返し(返礼品)を用意するのが一般的です。
香典返しの相場
いただいた金額の1/3〜半額程度が目安
3,000円〜5,000円程度の品物が一般的
返礼品の選び方香典返しには、以下のような品物がよく選ばれます。
お茶やコーヒーの詰め合わせ
のり・かつお節などの食品
カタログギフト(高額の香典をいただいた場合)
返礼品を渡すタイミング
当日返し:法要の際に受付で渡す(即日返し)
後日返し:法要後、1か月以内に郵送で送る
お礼の言葉(香典返しを渡す際の挨拶)「本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。心ばかりの品ですが、お受け取りください。」
香典返しの挨拶状の例文
後日お返しをする場合は、品物と一緒に挨拶状を添えます。
例文:「このたびは、○○(故人の名前)の法要に際しまして、温かいお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、心ばかりの品をお送りいたします。今後とも変わらぬご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。」
お布施や御香典のお礼は、感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことが大切です。
4.3 法事後の挨拶とお礼状の書き方
法事が終わった後は、参列者やお世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えることが大切です。直接の挨拶やお礼状を通じて、丁寧に感謝の意を表しましょう。
法事後の挨拶の仕方
法事が終わった後、参列してくれた方々には、感謝の言葉を伝えながらお見送りをします。また、遠方から来た方や特にお世話になった方には、後日電話や手紙で改めてお礼を伝えると丁寧な印象になります。
法事後のお礼状の書き方
法事に参列してくださった方や、御香典・お供えをいただいた方には、お礼状を送るのが一般的です。
お礼状の基本構成
冒頭の挨拶(季節の挨拶や相手の健康を気遣う言葉)
法要を無事に終えたことの報告
御香典やお供えに対するお礼
今後のお付き合いをお願いする言葉
お礼状を送るタイミング
お礼状は、法事が終わってから1週間以内に送るのが理想的です。香典返しを郵送する場合は、お礼状を添えると、より丁寧な印象になります。
法事後のお礼は、感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。形式よりも心を込めた言葉でお伝えするようにしましょう。
▶︎5. まとめ
法事は、故人を偲び、供養の気持ちを形にする大切な時間です。作法やマナーを守ることはもちろんですが、何よりも故人への想いを大切にすることが重要です。
形式よりも故人を想う気持ちが大切
法事にはさまざまな作法がありますが、最も大切なのは「故人を大切に思う心」です。形式的なことにとらわれすぎず、家族や参列者が心を込めて供養できるような時間を作ることが大切です。
遺族や参列者とのつながりを大切に
法事は、故人を偲ぶだけでなく、遺族や親族、友人とのつながりを深める機会にもなります。久しぶりに集まる親族と故人の思い出を語り合いながら、温かい気持ちで供養の時間を過ごしましょう。
無理のない形で継続することが大切
法事の回数や規模は、家庭の状況に応じて無理のない形で続けることが大切です。すべての回忌法要を必ず行う必要はなく、家族が納得できる形で供養を続けることが故人にとっても良い供養となります。
法事は、遺された人々が故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるための大切な時間です。形式にとらわれすぎず、心を込めた供養を心がけましょう。
▶︎法事の準備やご相談は迎福寺へ
法事を執り行うにあたって、「準備の仕方がわからない」「マナーが不安」などのお悩みはありませんか?迎福寺では、ご家族のご希望に寄り添いながら、心を込めた法要をお手伝いさせていただきます。
法事のご相談やご予約は、迎福寺の公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。経験豊富な僧侶が、故人様の供養をしっかりとお手伝いいたします。

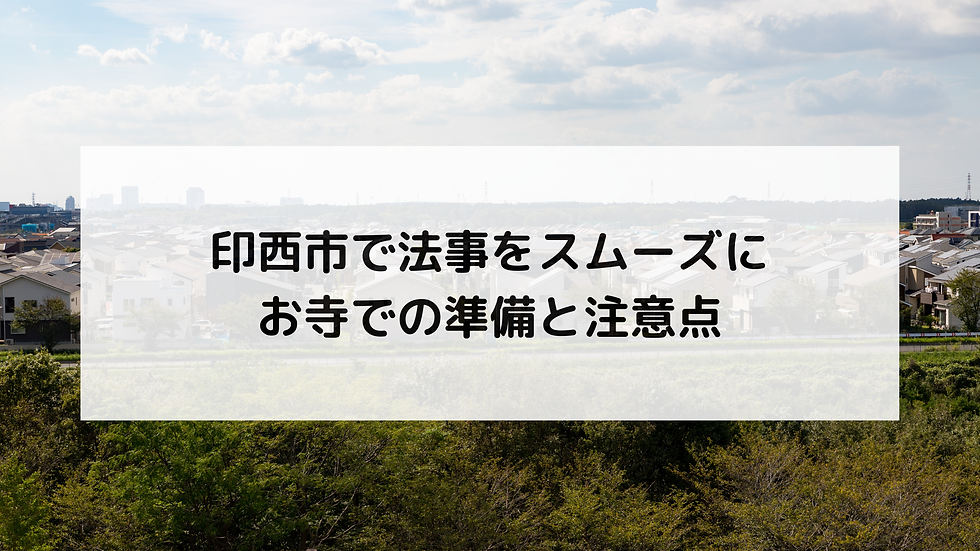

コメント