法事のお布施相場はいくら?金額の目安や渡し方を解説!
- 宗教法人迎福寺
- 2025年2月24日
- 読了時間: 17分

▶︎1. 法事のお布施とは?

1.1 法事におけるお布施の意味と役割
お布施は、僧侶への感謝の気持ちを表す大切なものです。 法事では、故人を偲び供養するために読経が行われます。その読経をしてくださる僧侶に対し、感謝の気持ちを込めてお渡しするのが「お布施」です。
お布施は「謝礼」ではなく「供養の一環」
お布施は、単なる謝礼とは異なります。本来、お布施は仏教の「布施行(ふせぎょう)」という教えに基づいており、「自分ができる範囲で他者に施しをする」ことが根本的な考え方です。したがって、法事におけるお布施も「読経をしていただく対価」ではなく、「供養の一環」として行うものなのです。
僧侶と仏教の教えを支える役割
お布施には、僧侶の生活を支える意味もあります。日本では、多くの僧侶が檀家や信者の方々からのお布施によって生計を立てています。お布施をお渡しすることで、僧侶の活動を支援し、仏教の教えが次の世代にも伝えられていくのです。
また、寺院は地域社会においても重要な役割を担っています。供養だけでなく、人生の節目での祈願や、地域住民の心の拠り所としての役割もあります。お布施を通じて、そのような寺院の活動を支えることにもつながります。
まとめ
法事のお布施は、僧侶に読経をお願いするための「料金」ではなく、仏教の教えに基づいた「感謝と供養の気持ち」を表すものです。その意味を理解したうえで、お布施を用意することが大切ですね。
1.2 お布施の基本的な考え方
お布施は「施しの心」を大切にする仏教の教えに基づいています。 そのため、「決まった金額を支払う」というよりも、「自分の気持ちや経済状況に応じてお渡しする」という考え方が基本です。とはいえ、相場を知っておくことで、適切な額を準備しやすくなります。
お布施は「見返りを求めない施し」
お布施の根本には、見返りを求めない「施し」の精神があります。仏教における「布施」は、金銭や物品を施すことに限らず、他者に対して善意を持って接することも含まれます。僧侶が読経をしてくださることも「仏法を説く布施」とされ、それに対するお布施は「感謝の気持ちを形にしたもの」と考えられています。
お布施の金額に決まりはない
お布施は「読経の対価」ではなく、あくまで「供養の心を表すもの」なので、明確な金額の決まりはありません。基本的には、施主の経済状況や気持ちに応じた額を包むのが一般的です。ただし、あまりに少額だと失礼に当たるのではと心配される方も多いため、多くの人が相場を参考にしています。
地域やお寺によっては、「これくらいが一般的です」と目安を示してくれることもあります。迷った場合は、菩提寺や親族に相談すると安心です。
まとめ
お布施は、読経に対する「料金」ではなく、「感謝と供養の気持ち」を示すものです。そのため、決まった額はなく、自分のできる範囲でお渡しするのが基本です。ただ、相場を知っておくことで適切な額を準備しやすくなるため、次の章で詳しく解説していきます。
▶︎2. 法事のお布施の相場

2.1 初七日・四十九日法要のお布施相場
初七日や四十九日の法要では、一般的に数万円程度のお布施を包むことが多いです。 ただし、地域やお寺によって異なるため、事前に確認するのが安心です。
初七日のお布施相場
初七日は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。最近では、火葬後すぐに初七日の法要を行う「繰り上げ初七日」が一般的になっています。
・お布施の相場:3万円~5万円
・御車代や御膳料を別途渡す場合もある
お布施のほかに、僧侶が遠方から来られる場合は「御車代」、会食を伴う場合は「御膳料」を用意することが多いです。
四十九日のお布施相場
四十九日は、忌明けの大切な法要です。納骨をこの日に行うことも多いため、お寺や僧侶へのお布施もやや高めに設定されることがあります。
・お布施の相場:3万円~10万円
・寺院によっては戒名料が別途必要
四十九日法要では、納骨を伴う場合があり、その際に「墓前での読経」や「戒名の授与」が行われることもあります。特に戒名を新たに授かる場合は、戒名料が別途かかるため注意が必要です。
お布施の金額はお寺に確認を
初七日や四十九日のお布施は、あくまで目安であり、お寺や僧侶によって異なります。檀家である場合は、これまでの慣習に従うのが良いでしょう。また、菩提寺がある場合は、事前に相談しておくと安心です。
まとめ
初七日や四十九日の法要では、一般的に3万円〜10万円程度のお布施を用意することが多いです。ただし、お寺や地域によって異なるため、事前に確認するのが大切です。また、御車代や御膳料、戒名料が必要な場合もあるので、合わせて準備しておきましょう。
2.2 一周忌・三回忌など年忌法要のお布施相場
一周忌や三回忌などの年忌法要では、一般的に3万円~5万円程度のお布施を包むことが多いです。 ただし、法要の規模やお寺の習慣によっても異なります。
一周忌のお布施相場
一周忌は、故人が亡くなってから1年後に行う大切な法要です。親族や親しい友人が集まり、僧侶に読経をお願いするのが一般的です。
・お布施の相場:3万円~5万円
・僧侶が遠方から来る場合は御車代を準備
・法要後の会食をする場合は御膳料も用意
一周忌は四十九日法要と同じくらい重要な法要とされるため、お布施の額も比較的高めにするのが一般的です。
三回忌以降のお布施相場
三回忌以降の法要は、故人を供養する節目として行われますが、一周忌よりも規模を小さくするケースが多くなります。そのため、お布施の金額もやや下がる傾向があります。
・お布施の相場:2万円~5万円
・家族だけで行う場合は少額でも問題なし
・大勢を招く場合は一周忌と同じくらいの額を用意
三回忌の後は、七回忌・十三回忌・十七回忌と続きますが、これらの法要は家族だけで行うことも増えており、その場合はお布施の額も1万円~3万円程度にすることが多いです。
お寺の意向に合わせるのがベスト
年忌法要のお布施は、各家庭の事情や地域の習慣によって大きく異なります。檀家になっているお寺がある場合は、あらかじめ相談しておくと適切な金額を把握できます。また、親族や経験者に尋ねるのも参考になりますね。
まとめ
一周忌や三回忌のお布施は、2万円〜5万円程度が一般的です。一周忌は四十九日法要と同様に重要視されるため、3万円以上包むことが多いです。三回忌以降は、規模に応じて額を調整すると良いでしょう。また、御車代や御膳料が必要な場合もあるので、合わせて準備しておくのが安心です。
2.3 地域や宗派によるお布施の違い
お布施の金額は、地域や宗派によって異なることがあります。 一般的な相場を参考にすることは大切ですが、地域の習慣や宗派の考え方も理解しておくと安心です。
地域によるお布施の違い
日本各地で法要の習慣が異なるように、お布施の金額にも地域差があります。都市部では比較的高額になる傾向があり、地方では少し抑えめになることが多いです。
・都市部(東京・大阪など) … 5万円~10万円
・地方(東北・九州など) … 3万円~5万円
・寺院との関係性が深い地域 … 金額が高めになることも
また、地方では檀家制度が根強く残っているため、お寺との関係性によってもお布施の金額が変わることがあります。長くお付き合いのあるお寺では、相場より高めに包むケースも少なくありません。
宗派によるお布施の違い
宗派によっても、お布施の考え方や金額に違いがあります。例えば、浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」を授かるため、戒名料が不要な場合が多いです。一方で、真言宗や天台宗では、戒名の位によってお布施が変わることがあります。
・浄土真宗 … 戒名料なし、法名を授かる
・曹洞宗・臨済宗 … 一般的な戒名料が必要
・真言宗・天台宗 … 位の高い戒名を希望する場合、高額になる
また、お寺によっては、「お布施の額は施主の気持ち次第」とされ、特に決まりがないこともあります。逆に、「〇万円以上が目安」と具体的に提示されていることもあるため、事前に確認すると安心です。
まとめ
お布施の金額は、地域や宗派によって異なります。都市部では高め、地方ではやや抑えめの傾向があり、お寺との関係性によっても変わります。宗派によっては戒名料の有無なども異なるため、まずは菩提寺や親族に相談し、適切な額を準備するのがよいでしょう。
▶︎3. お布施の包み方と渡し方

3.1 お布施を包む際のマナーと表書きの書き方
お布施を包む際には、適切な封筒を使い、表書きを正しく記載することが大切です。 また、渡す際のマナーも心得ておくと安心です。
お布施を包む封筒の選び方
お布施は、通常「白無地の封筒」または「水引のない奉書紙」で包みます。コンビニや文具店で売られている「お布施用の封筒」でも問題ありません。
・正式な包み方 … 奉書紙に包み、白封筒に入れる
・略式の包み方 … 市販の「お布施」用封筒を使用
香典袋のような「黒白や双銀の水引が付いたもの」は使用しません。これは、お布施が「謝礼」ではなく「感謝の気持ちを表すもの」であり、供養の一環だからです。
お布施の表書きの書き方
お布施の封筒には、表書きを記載します。基本的に、薄墨ではなく「黒墨」で書くのが一般的です。
・表書き(上段) … 「お布施」または「御布施」
・氏名(下段) … 施主(喪主)の名前をフルネームで記載
特定の宗派では、表書きが異なる場合があります。例えば、浄土真宗では「御礼」と記載することもありますので、事前に確認するとよいでしょう。
お札の入れ方
お布施を封筒に入れる際、お札の向きにも注意します。
・新札を避ける(新札は「準備していた」という印象を与えるため)
・お札の向きを揃える(肖像画がある面を封筒の表側に向ける)
地域やお寺の習慣によって細かいマナーは異なることがあるため、事前に確認するとより丁寧です。
まとめ
お布施は、白無地の封筒または奉書紙に包み、表書きを「お布施」と記載します。新札は避け、お札の向きを揃えるのがマナーです。適切な包み方を知って、心を込めて準備しましょう。
3.2 お布施を渡すタイミングと作法
お布施は、法要の始まる前に僧侶へ直接手渡しするのが一般的です。 また、渡す際には丁寧な作法を心がけることで、より気持ちのこもった対応ができます。
お布施を渡すタイミング
お布施を渡すのは、法要が始まる前が基本です。僧侶が到着し、挨拶を交わしたあと、読経が始まる前のタイミングで渡します。
・法要の前に渡すのが基本
・お寺で法要を行う場合は、本堂に入る前や控え室で渡すことが多い
・僧侶が帰る間際は慌ただしいため、事前に渡すのが望ましい
どうしても渡すタイミングを逃してしまった場合は、法要後に「本日はありがとうございました」とお礼を述べながらお渡しすれば問題ありません。
お布施の正しい渡し方
お布施は、封筒をむき出しのまま渡すのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す直前に取り出します。
お布施を渡す手順
袱紗に包んだお布施を持参する
渡すときに袱紗から取り出し、封筒を両手で持つ
「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と丁寧に挨拶する
僧侶の前にそっと差し出す
このとき、封筒の表書き(「お布施」と書かれた面)を僧侶側に向けて渡すと、より丁寧な作法になります。
渡すときの言葉遣い
お布施を渡す際は、シンプルで丁寧な言葉を添えましょう。
・「本日はよろしくお願いいたします」
・「どうぞお納めください」
・「ささやかですが、お納めいただければ幸いです」
「受け取ってください」や「お渡しします」などの表現は、やや事務的に聞こえるため避けた方がよいでしょう。
まとめ
お布施は、法要の始まる前に袱紗から取り出し、両手で丁寧に渡します。渡すときは「どうぞお納めください」などの言葉を添えると、より丁寧な印象になります。僧侶への感謝の気持ちを込めて、マナーを意識しましょう。
▶︎4. お布施以外に必要な費用
4.1 御車代と御膳料の相場
法事では、お布施のほかに「御車代」や「御膳料」を用意するのが一般的です。 これらは僧侶の移動費や食事代としてお渡しするものですが、地域や状況によって金額が異なります。
御車代の相場
御車代とは、僧侶が自宅や墓地へ来て読経を行ってくれた際に、お礼として渡す交通費のことです。
・相場:5,000円~10,000円・遠方から来られる場合は1万円以上にすることもある
・お寺で法要を行う場合は不要
御車代は、お布施とは別の封筒に入れて渡します。表書きは「御車代」または「御車料」とし、お布施と同じように袱紗に包んで持参すると丁寧です。
御膳料の相場
御膳料とは、本来なら法要後に僧侶と一緒に食事をするところを、代わりに渡すお礼のことです。
・相場:5,000円~10,000円・食事を用意する場合は不要
・僧侶が辞退された場合も、無理に渡さなくてよい
法要後に会食を予定している場合は、僧侶にも声をかけるのが礼儀です。もし辞退された場合は、「御膳料」としてお礼をお渡しすることが多いですが、事前にお寺へ確認しておくとよいでしょう。
御車代・御膳料を渡すタイミング
御車代と御膳料は、お布施と一緒に渡すのが一般的ですが、別々の封筒に入れておくことが重要です。
・お布施と一緒に渡す(法要の前にお渡しする)
・御膳料は、法要後に渡すこともある
・それぞれの封筒に分けて用意する
僧侶によっては「お気持ちだけで十分です」と辞退される場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ
御車代と御膳料は、それぞれ5,000円~10,000円程度が相場です。お布施とは別の封筒に入れて準備し、法要の前後で適切なタイミングで渡しましょう。事前にお寺へ確認し、無理のない範囲で用意することが大切です。
4.2 戒名料やその他の費用について
法事では、お布施や御車代・御膳料のほかに「戒名料」などの費用がかかる場合があります。 事前に確認し、適切な準備をしておくと安心です。
戒名料の相場
戒名料は、故人に戒名を授けてもらう際にお渡しするお布施の一種です。戒名の位(ランク)によって金額が異なることが一般的です。
・信士・信女(一般的な戒名)… 10万円~30万円
・居士・大姉(やや格式の高い戒名)… 30万円~50万円
・院号付き(格式の高い戒名)… 50万円以上
戒名の種類によって費用が変わるため、事前にお寺に相談するのがよいでしょう。なお、浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼び、無料または比較的安価で授けられることもあります。
その他の費用
法事では、戒名料のほかにも以下のような費用が発生することがあります。
・納骨供養のお布施(納骨を伴う場合)… 3万円~5万円
・塔婆料(卒塔婆を立てる場合)… 3,000円~10,000円
・お墓参りの際の読経料(墓前供養)… 5,000円~1万円
お寺や地域の慣習によって金額は異なりますので、事前に確認するのがベストです。
まとめ
戒名料の相場は、戒名の位によって10万円~50万円以上と幅があります。また、納骨供養や塔婆料など、法事に関連する費用が発生することもあります。お寺の慣習を確認し、無理のない範囲で準備することが大切です。
▶︎5. 法事のお布施でよくある疑問
5.1 お布施の額に決まりはあるの?
お布施の金額には厳密な決まりはなく、「施主の気持ちや経済状況に応じてお渡しする」のが基本です。 ただし、一般的な相場があるため、それを参考にしながら準備すると安心です。
お布施の金額は「気持ち」を表すもの
お布施は、読経の「対価」ではなく、感謝の気持ちを表すものとされています。そのため、「必ず〇〇円でなければならない」という決まりはありません。ただし、法要の種類によって、ある程度の目安は存在します。
・初七日・四十九日法要 … 3万円~10万円
・一周忌・三回忌 … 2万円~5万円
・納骨法要 … 3万円~5万円
地域やお寺によって異なるため、事前に菩提寺や親族に相談するのもよいでしょう。
「金額が少なすぎると失礼」なのか?
お布施の額が少なすぎると「失礼にあたるのでは?」と心配される方も多いですが、過度に気にする必要はありません。お寺によっては「お気持ちで結構です」とされる場合もあります。
ただし、一般的な相場よりも極端に低い額を包むと、「感謝の気持ちが足りない」と受け取られてしまう可能性もあります。そのため、最低限の目安を意識しておくと安心です。
「高額すぎると逆に失礼」になることも
一方で、相場を大きく超える高額なお布施を包むと、お寺によっては「負担に感じる」と捉えられることもあります。特に、普段からお付き合いのあるお寺では、適正な額を心がけることが大切です。
高額にする場合は、事前にお寺へ相談し、「このような額で失礼がないか」と確認しておくとよいでしょう。
まとめ
お布施の金額に厳密な決まりはありませんが、相場を参考にしながら準備するのが一般的です。金額が少なすぎると気になるかもしれませんが、高すぎてもお寺によっては負担になることがあります。適正な額を意識しつつ、事前に相談すると安心ですね。
5.2 お布施を渡す際の服装や立ち振る舞い
お布施を渡す際は、相応しい服装を心がけ、丁寧な立ち振る舞いでお渡しすることが大切です。 形式ばった作法を気にしすぎる必要はありませんが、基本的なマナーを押さえておくと安心です。
お布施を渡す際の服装
法事では、施主や参列者は基本的に喪服を着用することが多いため、お布施を渡す際もそのままの服装で問題ありません。ただし、法事ではなく日常的な仏事(お寺へのお参りや年末の挨拶など)でお布施を渡す場合は、落ち着いた服装を意識しましょう。
・法事の際 … 喪服(ブラックフォーマル)が基本
・お寺への訪問時 … 地味な色合いのスーツや落ち着いた服装
・カジュアルすぎる服装はNG(ジーンズ、Tシャツ、派手な柄の服など)
お寺によっては、あまり格式ばる必要がない場合もありますが、最低限の礼儀として清潔感のある服装を心がけましょう。
お布施を渡す際の立ち振る舞い
お布施は、封筒をそのまま手渡しするのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す直前に取り出して手渡すのが正式なマナーです。
お布施の渡し方の手順
袱紗に包んで持参する
渡す際に袱紗を開き、封筒を取り出す
両手で封筒を持ち、僧侶の前に差し出す
「本日はよろしくお願いいたします」「どうぞお納めください」と一言添える
また、お布施の封筒の向きにも注意が必要です。封筒の表書きを僧侶側に向けて渡すと、より丁寧な印象になります。
渡す際に気をつけたいこと
お布施を渡す際、以下の点に気をつけるとより礼儀正しい印象を与えます。
・封筒を乱雑に扱わない(ポケットやバッグから直接取り出さない)
・片手ではなく、必ず
両手で渡す・感謝の気持ちを込めた言葉を添える
また、「つまらないものですが」「ほんの気持ちですが」といった謙遜の言葉は、お布施にはふさわしくありません。シンプルに「どうぞお納めください」と伝えるのが適切です。
まとめ
お布施を渡す際は、法事なら喪服、それ以外でも落ち着いた服装を心がけましょう。袱紗に包んで持参し、封筒を取り出して両手で丁寧に渡すのが正式な作法です。渡す際には一言添えると、より心のこもった対応になります。
▶︎6. まとめ:適切なお布施で心を込めた法要を
お布施は、僧侶への感謝の気持ちを形にする大切なものです。 そのため、単なる「読経の対価」としてではなく、故人の供養の一環として心を込めて準備することが大切です。
お布施の基本を振り返る
お布施の金額や渡し方には一定のマナーがありますが、最も重要なのは「感謝の気持ち」です。改めて、お布施に関するポイントを振り返りましょう。
・お布施の相場 … 法事の種類に応じて 2万円~10万円 程度が一般的
・御車代や御膳料 … 僧侶の移動費や食事代として 5,000円~1万円 程度を用意
・戒名料 … 位によって 10万円~50万円以上 かかることも
・封筒のマナー … 白無地の封筒や奉書紙を使用し、表書きは「お布施」と記載
・渡し方の作法 … 袱紗に包んで持参し、両手で丁寧に渡す
地域やお寺の習慣によって細かい違いがあるため、不安な場合は事前に確認するのがベストです。
法事を通じて故人を偲ぶ
法事は、故人を供養する大切な時間です。お布施の額や作法にとらわれすぎず、何よりも「故人を想う心」を大切にしましょう。適切なお布施を用意し、僧侶やお寺の方々への感謝を伝えることで、より意義のある法要となります。
▶︎法事のことでお悩みなら、迎福寺にご相談ください
法事のお布施の相場やマナーについて、不安に感じることはありませんか? 迎福寺では、故人の供養を大切に考え、一人ひとりのご事情に寄り添った法要をお手伝いしております。
お布施の金額や包み方、渡し方などについても丁寧にご案内いたしますので、安心してご相談ください。ご希望に応じて法要の準備もサポートいたします。
法事のご依頼やご相談は、迎福寺までお気軽にお問い合わせください。

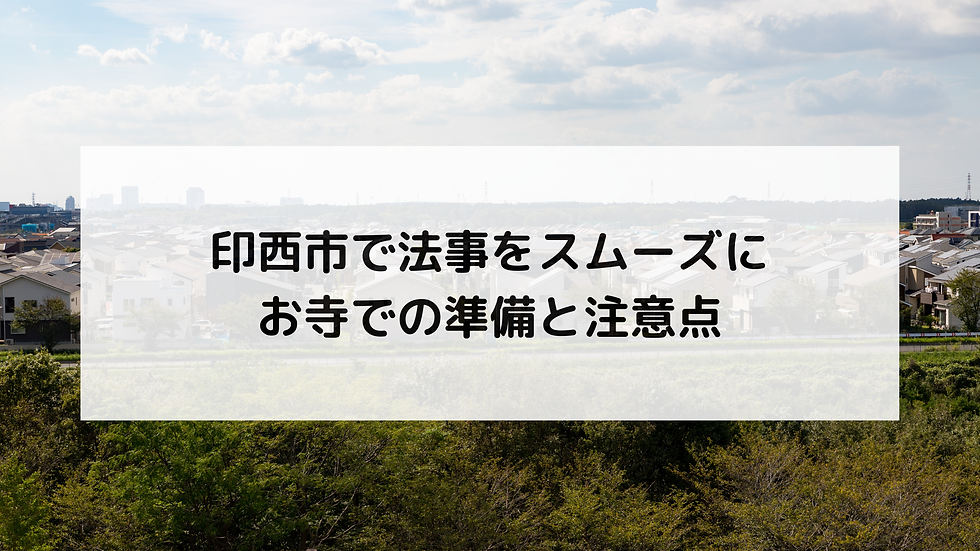

コメント